協働性とは、仲間と力を合わせて共通の目標を達成する力のことです。
これからの社会では、学校生活はもちろん、将来の仕事の場でも欠かせない力として注目されています。
たとえば、友達と意見を出し合いながら作品を作るような場面でも、協働性が育っている子どもほど、自然にチームをまとめることができます。
 ゆうりんママ
ゆうりんママ一方で、「協調性との違いがよく分からない」「家庭でどうやって伸ばせばいいのか見当がつかない」と感じる方も少なくありません。
今回は、協働性についてお伝えしていきますね。
- 協働性とは?協調性との違い
- 子どもの協働性を育むメリットと親ができること
- 協働性を高めるおすすめの習い事
協働性の正確な意味と協調性との違い、子どもの協働性を育むメリット、そして家庭で今日から実践できる具体的な方法まで分かりやすく解説します。
さらに、協働性を高める習い事も厳選して紹介しますので、お子さんに合ったヒントがきっと見つかるはずです。
是非最後までご覧ください。
協働性とは?子どもの未来に必要な力


子どもが将来、社会の中で自分らしく生き生きと活躍するためには、「協働性」を育むことが欠かせません。
現代社会では、一人でできることよりも、チームとして成果を出すことが求められる場面が増えています。
学校でも、グループで話し合いながら学ぶ「協働的な学び」が重視され、2025年現在、文部科学省はICTを活用して「個別最適な学び」と「協働的な学び」を融合させています。
子どもたちは互いの意見を尊重しながら考えを深める力を養っています。



家庭や遊びの中でも、この協働性は自然に育つ力です。
ここでは、協働性の意味と、なぜ今この力がこれほど注目されているのかを分かりやすく解説します。
協働性の意味と具体例
協働性とは、異なる個性や能力を持つ人たちが、それぞれの強みを生かしながら、共通の目標に向かって協力する力のことです。
単に「仲良くする」ことや「周囲に合わせる」ことではなく、自分の役割を理解し、主体的に考え、行動しながら他者と力を合わせることが求められます。



たとえば、運動会での大玉転がしを思い浮かべてみてください。
子どもたちは「押す人」「方向を伝える人」など役割を分担し、声を掛け合いながらゴールを目指します。
誰かが転んでも、仲間が助けて一緒に進む――そんな姿こそが協働性の表れです。



このように、協働性は特別な場面だけでなく、日常のあらゆる活動を通して自然に育まれる力なのです。
令和の子育てでは、「自分の意見を持つ+違う価値観と出会う」力が協働性の鍵。
多様な人との日常交流で育ち、家庭での「あなたはどう思う?」問いかけが特に効果的です。
なぜ今、協働性が重視されるのか
協働性がこれほど重視されるようになったのは、社会全体が大きく変化しているからです。
教育、ビジネス、地域、そしてグローバルな環境――いずれの場面でも「一人で完結できない課題」が増えています。
以下の表に、主な背景をまとめました。
| 分野 | 協働性が求められる背景 | 具体的な動き・変化 |
|---|---|---|
| 教育 | 一方的な授業から、対話・協力を重視する学びへ転換 | 「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」の導入。 グループワークや共同制作が増加。 |
| ビジネス | 複雑化・専門化する社会で、個人の力だけでは対応困難 | 経済産業省の「社会人基礎力」においても、「チームで働く力」が最重要スキルとして位置付けられている。 |
| 地域社会 | 少子高齢化や防災など、地域の課題を住民同士で支える必要性 | 子ども時代から協働性を育むことが、将来の地域貢献にもつながる。 |
| グローバル社会 | 異なる文化・価値観を超えて協力する機会が増加 | 国際的なプロジェクトやオンラインでの共同活動が当たり前に。 |



「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」の導入の部分が気になります。



この表では簡潔に記載していますが、根拠を知りたい方は、下記をご覧ください。
協働性を持つ人は、他者の意見を尊重しながら自分の考えを発信し、より良い解決策を生み出すことができます。
この力は、学びの場だけでなく、将来社会に出たときにも大きな強みになります。
協働性と協調性の3つの違い


「協働性」と「協調性」は似ているようで、実は目指す方向が異なります。
どちらも人間関係を築くうえで欠かせない力ですが、育て方のポイントを間違えると「仲良くできるけど行動できない子」や「自分勝手に動く子」になってしまうこともあります。



その違いを理解することは、子どもの将来に必要な力をバランスよく育てる第一歩です。
協働性と協調性の主な違いを簡潔に表にまとめましたのでご覧ください。
| 観点 | 協働性 | 協調性 |
|---|---|---|
| 目的 | 共通の目標を「達成」することを重視 | 集団内の「調和」を保つことを重視 |
| 行動の主体 | 自ら考え、提案し、行動する | 周囲に合わせて行動する |
| 役割の考え方 | 一人ひとりの強みを活かして分担 | 全員が平等に同じことを行う傾向 |



早速見ていきましょう。
違い:①目的の明確性(協働は目標達成、協調は調和重視)
最も大きな違いは、「何をゴールとするか」という目的の違いです。
協働性は、共通の目標を達成することを最優先します。
たとえば学校の文化祭で演劇をする場合、協働性が高いクラスでは「観客に感動してもらう」という明確な目標に向かって動きます。
主役を演じる子、大道具を作る子、音響を担当する子など、それぞれが自分の役割に責任を持ち、「どうすれば全体が良くなるか」を考えながら行動するのが協働性です。
一方、協調性は「みんなと仲良く」「誰も嫌な思いをしない」ことを重視します。
文化祭の準備でも、意見がぶつかりそうになると「まぁ、どっちでもいいよ」と譲ってしまうなど、衝突を避ける行動を取ります。
グループ発表の準備を例として挙げますので、下記をご覧ください。
- 協働性が高い子:「このデータを使うともっと分かりやすいよ」と積極的に提案し、自分の得意な部分を活かす。
- 協調性が高い子:「みんながそう言うなら、それでいいよ」と自分の意見を控える。



どちらも大切な力ですが、社会では「仲良くするだけ」でなく、「チームで成果を出す」ことが求められています。
これが協働性の本質です。
違い:②主体性の有無(協働は自ら考える、協調は合わせる)
協働性と協調性のもう一つの大きな違いは、「自分で考えて動くか」どうかです。
協働性を持つ子どもは、状況を見て自分で判断し、仲間と意見を交わしながらより良い方法を探ります。



例えばサッカーの試合中、「今はパスを回した方がいい」「ここはシュートを狙おう」と考え、チーム全体を見ながら行動します。
ミスをしても「次はこうしよう」と改善に向けて動くのが特徴です。
一方、協調性が高い子は、周りの意見を尊重しすぎるあまり、「自分の考え」を出さない傾向があります。



「キャプテンが言ったから」「みんながそうしてるから」と、場の流れに合わせることでトラブルは避けられますが、自分の意見を持つ力が育ちにくくなります。



協調性だけでは「言われたことはできるけれど、自分から新しいことを提案できない」状態になりがちということですね。



協働性を育てることで、「自分で考え、行動し、仲間と成果を出す」という、これからの社会に必要な力が身につきます。
違い:③役割分担の考え方(協働は強みを活かす、協調は平等に)
チームで作業をするとき、協働性と協調性では役割の分け方にも違いが出ます。
協働性では、一人ひとりの強みや得意分野を活かして役割を決めます。
たとえば、クラスで壁新聞を作る場合を例に挙げますので、下記をご覧ください。
- 絵が得意な子 → イラストを担当
- 文章が得意な子 → 記事を執筆
- 調べるのが得意な子 → 情報収集
- まとめるのが得意な子 → 全体構成を考える
このように得意分野を活かすことで、全員がやりがいを感じ、結果的に完成度の高い作品ができます。
一方、協調性を重視する場合は、「みんなが同じようにやる」ことを優先します。



全員が少しずつ絵を描き、少しずつ文章を書き、少しずつ調べる…。一見公平ですが、得意でない作業をすることで時間がかかったり、責任の所在が曖昧になったりすることもあります。
得意なことを任されることで子どもの意欲も高まり、「自分がチームの役に立っている」という自信が育ちます。



協調性は、人間関係を円滑にするための“基盤”ですね。
その上に、協働性という“行動の力”を積み上げることで、子どもはチームの中で輝ける存在になります。



理想は、「仲間と仲良くしながら、自分の意見を持ち、チームの目標に向かって行動できる子」ではないでしょうか。
子どもの協働性を育む8つのメリット


協働性を育てることは、子どもの未来に大きな力を与えます。
仲間と一緒に考え、支え合い、力を合わせて目標を達成する経験は、単なる人間関係のスキルにとどまらず、子どもの内面の成長にも深くつながります。
自己肯定感が高まり、自信を持って行動できるようになったり、人の気持ちを理解し思いやる力が育ったりと、協働性は子どもの「生きる力」を支える土台です。



さらに、協働を通して得られる学びは、将来の学習意欲や社会適応力にも影響します。
これからの時代、**AIでは代替できない「人と協力する力」こそが、最も価値ある力と言われていますよね。
ここでは、協働性を育てる8つの具体的なメリットを紹介します。
メリット:①自己肯定感が高まり自信がつく
協働性を育てると、子どもの「自分は役に立っている」という感覚が芽生えます。



なぜ自己肯定感が高まるんですか。



協働の場面では、一人ひとりが役割を持ち、その役割を果たすことでチーム全体に貢献します。
「自分の力がみんなの役に立った」「自分がいたから成功できた」という実感は、子どもの自己肯定感を強く育てます。
小学3年生のタクヤくんは運動が苦手でしたが、リレーの作戦会議で「バトンの受け渡しを丁寧にする」という役割を任されました。
クラスが優勝し、友達に感謝されたことで「自分にもできることがある」と自信を持つようになりました。
幼少期にこうした成功体験を重ねることは、思春期以降のストレス耐性やメンタルヘルスの安定にも良い影響を与えます。
メリット:②良好な人間関係を築ける
協働性が育つと、相手の立場を考え、思いやりのある関係を築く力が自然に身につきます。
一緒に活動する中で、「相手の気持ちを理解する」「意見が違っても受け入れる」などの経験を通して、コミュニケーション能力が高まるといわれていることが理由です。
協働性の高い子どもは、共感力・表現力・傾聴力・交渉力といった対人スキルをバランスよく育て、学校でも将来の職場でも人間関係を築くのが得意になります。
メリット:③問題解決力と創造力が育つ
協働の場では、課題をどう解決するかを仲間と一緒に考えます。
その過程で、論理的に考える力や柔軟な発想力が育つといわれているからです。
複数の意見やアイデアに触れることで、「こんな考え方もあるんだ」と視野が広がり、より創造的な解決策を生み出せるようになります。
小学5年生のクラスで、「校庭の隅にある使われていない花壇をどう活用するか」という課題が出されました。
個人で考えた時は「花を植える」「野菜を育てる」といった一般的なアイデアしか出ませんでしたが、グループで話し合った結果、「昆虫が集まる花を植えて観察できる場所にする」「地域の高齢者と一緒に野菜を育てて交流の場にする」といった創造的なアイデアが次々と生まれました。



協働的な活動は、一人では得られない「集合知」の効果を発揮し、創造力を伸ばす土台になりますよ。
メリット:④学習意欲が向上する
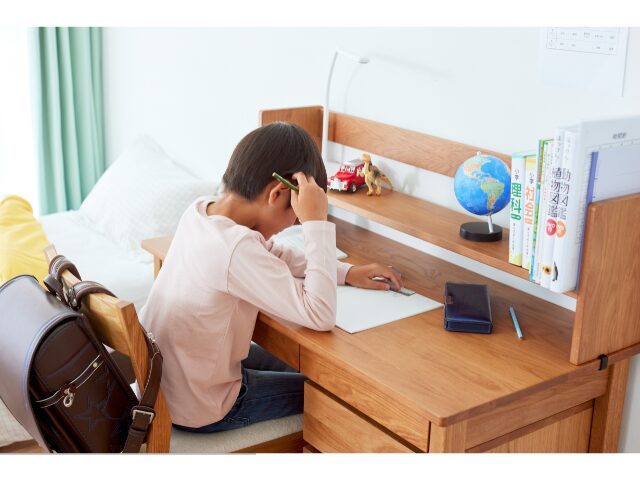
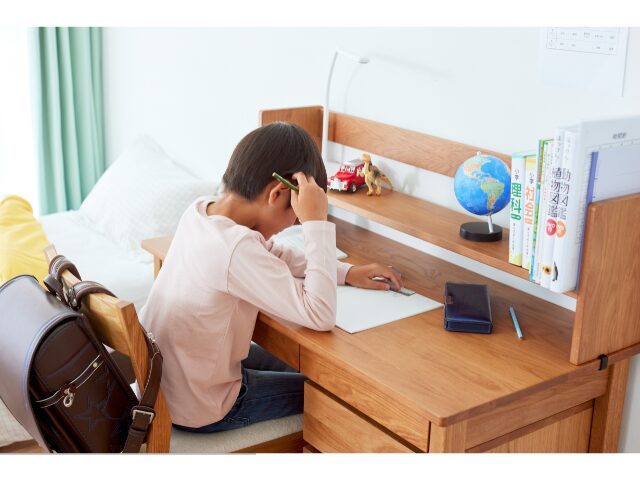
仲間と一緒に学ぶことで、学びが楽しくなります。



「分からないところを教え合う」「一緒に挑戦する」といった経験は、勉強への前向きな姿勢を育てますよね。



文部科学省の調査によると、「友達と協力して学ぶことが多い」と答えた子どもほど、学力が高い傾向があるそうです。
協働的な学習では、子どもたちが自然に教え合う場面が生まれるため、学んだ内容が深く定着します。
このような学び方は、「教えてもらう」だけの受け身な勉強から、「自分たちで考え、学び合う」主体的な学びへと子どもを導くきっかけにもなります。
メリット:⑤コミュニケーション能力が高まる
協働の場では、常に会話や意見交換が求められます。



自分の考えを言葉で伝えたり、相手の話を最後まで聞いたりする経験を繰り返すうちに、自然とコミュニケーション能力が磨かれますよね。
具体例を見ましょう。
小学4年生のアヤちゃんは、自分の意見を言うのが苦手でした。
しかし、クラスで「読書感想を3人グループで発表し合う」という活動を続けるうちに、「私はこう思った」と自分の意見を言えるようになりました。
最初は緊張していましたが、友達が「それいいね!」「私はこう思うよ」と反応してくれることで、「自分の意見を言っても大丈夫なんだ」という安心感を得ました。
今では、クラス全体の前でも堂々と発表できるようになっています。
これからの時代、対面だけでなくオンラインでも意思を伝える力が求められるでしょう。
協働性は、どんな環境でも人と関わるための基礎になります。
メリット:➅リーダーシップが身につく
協働性が高い子どもは、自然とリーダーシップを発揮できるようになります。



なぜリーダーシップが育つのでしょうか。
協働の場面では、時にはリーダー役を担当することもあれば、フォロワー役を担当することもあります。
様々な役割を経験することで、「どうすればチームをまとめられるか」「どうすればメンバーの力を引き出せるか」を学びます。



ここで重要なのは、リーダーシップとは「命令する力」ではなく、「メンバーの力を引き出し、目標達成に導く力」だということです。
協働を通じて、子どもは本質的なリーダーシップを学びます。
中学2年生のケンタくんは、文化祭でクラスの出し物のリーダーを任されました。
最初は「みんなをまとめられるか不安」と感じていましたが、「一人ひとりの意見を聞く」「それぞれの得意なことを活かす役割分担をする」「困っているメンバーをサポートする」ことを心がけた結果、クラス全員が協力して素晴らしい出し物を完成させることができました。
この経験を通じて、ケンタくんは「リーダーとは、みんなの力を引き出す存在なんだ」と理解しました。
こうした経験は、「人を導く力」と「人を支える力」の両方を育てます。
メリット:⑦多様性を受け入れる力が育つ
協働性を育むことで、子どもは多様性を受け入れ、尊重する力が身につきます。



なぜ多様性を受け入れられるようになるのでしょうか。



協働の場面では、様々な個性や能力を持つ仲間と関わりますよね。「自分とは違う考え方がある」「得意なことも苦手なこともみんな違う」という経験を重ねることで、多様性を自然と受け入れられるようになります。
これからの時代、日本国内でも外国人労働者が増加し、多様な価値観を持つ人々と協働する機会が増えるのは確実です。
幼少期から多様性を受け入れる経験をすることは、グローバル社会で活躍するための重要な基盤となります。
多様性を受け入れる力は、単に「違いを認める」だけでなく、「違いを価値として活かす」ことまで含み、協働の経験を通じて、子どもは「みんな違って、みんないい」という包摂的な価値観を育てることができます。
メリット:➇将来の社会適応力が高まる
協働性を育むことで、子どもの将来の社会適応力が大きく向上します。



なぜ社会適応力が高まるのか知りたいですよね。
社会に出ると、学校とは違う様々な場面で協働が求められるからです。
職場でのプロジェクト、地域活動、家庭内での役割分担など、協働する機会は無数にあります。
幼少期から協働の経験を積むことで、どんな環境でも柔軟に適応し、他者と協力して課題を解決する力が育ちます。



長期的な追跡調査では、子どもの頃に協働的な活動に積極的に参加していた人は、成人後の仕事満足度や人生満足度が高い傾向が報告されています。



現代は、技術革新や社会変化のスピードが非常に速く、「正解のない問題」に直面することが増えていますよね。
協働性が高い人は、仲間と協力しながら試行錯誤し、新しい解決策を見つけ出すことができます。
協働性を育てることで、以下のような社会適応力が身につきます。
1. 環境適応力:新しい環境でも、すぐに人間関係を築ける
2. ストレス耐性:困難な状況でも、仲間と協力して乗り越えられる
3. キャリア形成力:職場で信頼され、重要な役割を任される
4. 人生満足度:良好な人間関係を築き、充実した人生を送れる
協働性は、一度身につければ生涯にわたって役立つ力です。
職場だけでなく、家庭を築く時、地域社会に参加する時、趣味のグループに入る時など、人生のあらゆる場面で協働性が求められます。
子どもの頃から協働性を育てることは、その子の人生全体を豊かにする投資と言えるでしょう。
子どもの協働性を育むために親ができること


ここまで見てきたように、協働性は「仲間と力を合わせて目標を達成する力」であり、これからの社会でますます求められる大切な資質です。
しかし、協働性は学校の授業だけで自然に身につくものではなく、実は家庭の中の小さな関わりから育まれていきます。
親が日常の中で「協力の喜び」や「相手を思いやる姿勢」を見せることで、子どもは協働の意味を体感的に理解していきます。



ここでは、特別な教材や難しい指導ではなく、家庭で今日からできる8つの実践方法を紹介しますね。
どれも親子で楽しみながら取り組める内容ばかりなので、無理なく続けることで、子どもの「協働する力」が自然と伸びていくはずです。
協働性を育む方法:①日常のお手伝いで協力する喜びを体験させる
家庭でのお手伝いは、協働性を育む最も身近で効果的な方法です。
お手伝いを通じて、子どもは「自分の行動が家族の役に立つ」という実感を得ます。
親と一緒に作業する中で、「協力すると早く終わる」「一緒にやると楽しい」という経験を重ねることで、協働の楽しさを自然と学んでいきます。



長期的な研究でも、幼少期から家事を手伝っていた子どもは、成人後に人間関係や仕事での協働力が高い傾向があると報告されていますよ。



6歳の子にはどんなお手伝いが良いですか?
- 3〜5歳:洗濯物をたたむ、テーブルを拭く、配膳の手伝い
- 6〜8歳:お風呂掃除、食器洗い、簡単な料理の手伝い
- 9〜12歳:掃除機がけ、料理を一品作る、弟妹の世話
最初は一人でやらせるのではなく、親と一緒に行うことが大切です。
「お母さんが洗うから、○○ちゃんは拭いてね」と役割を明確にし、終わったら「助かったよ、ありがとう」と感謝の言葉を具体的に伝えましょう。



うまくできなくても責めずに「一緒にやってくれて嬉しい」と伝えることで、子どもはお手伝いに前向きになります。
さらに「毎日夕食後に食器を運ぶ」といった習慣化をすると、自然と協働が生活の一部になります。



お手伝いは「家族の一員として役立つ」実感を得る最高の機会ですね。
成功体験を積み重ねることで、子どもは協働の楽しさを理解し、「人のために動く力」を身につけていきます。
協働性を育む方法:②家族の中で役割を与え責任感を育てる
子どもに継続的な「自分の仕事」を持たせることで、協働性と責任感を同時に育てることができます。



なぜ役割が重要なんですか。
一時的なお手伝いではなく、「これは自分の仕事」という継続的な役割を持つことで、子どもは「自分は家族の一員として必要な存在だ」という自覚を持ちます。
また、毎日続けることで責任感が育ち、「自分の役割を果たす」という協働の基本姿勢が身につきます。
- 幼児期(3〜5歳):ペットのエサやり、植物の水やり、玄関の靴を揃える
- 学童期(6〜12歳):ゴミ出し、お風呂の準備、洗濯物の取り込み、弟妹の送り迎え
「これは○○ちゃんの大切な仕事だよ」と役割の意味を伝えることが大切です。
最初は忘れてしまっても怒らず、「思い出せたら一緒にやろうか」と声をかけましょう。
また、成長に合わせて役割を少しずつ変えることで、子どもは自信と達成感を積み重ねていきます。
小学2年生のコウキくんは、毎朝「家族全員の朝食のお箸を並べる」役割を担当しています。
お母さんから「コウキくんがいないとみんな食べられないね」と言われたことで、自分の役割に誇りを持ち、今では自発的にお箸を並べるようになりました。



自分の役割を持つことは、子どもに「信頼されている」という自信を与えます。
小さな責任を果たす経験が積み重なるほど、協働の土台となる責任感と主体性が育っていきますよ。
協働性を育む方法:③地域活動やボランティアで多様な人と関わらせる


家庭や学校以外の場での協働経験は、子どもの社会性を広げます。



なぜ、地域活動が協働性を育てるのかわかりますか。
家庭や学校では、同じ年齢の子どもや顔見知りの大人との関わりが中心です。
しかし、地域活動やボランティアでは、様々な年齢層や背景を持つ人々と協働します。
この多様性の中で協働することで、「人それぞれ違う考え方がある」「年齢が違っても協力できる」という柔軟性が育ちます。
- 幼児期:公園の清掃、花壇の手入れ、地域イベントの手伝い
- 学童期:老人ホームでの交流、防災訓練、フードバンク活動
子どもの興味に合わせて活動を選び、最初は親も一緒に参加することで安心感を与えます。
活動後には「どんなことが楽しかった?」と話し合いながら、経験を振り返りましょう。
一度だけでなく継続的に参加することで、地域とのつながりも深まります。



異なる立場や年齢の人と協力する経験は、子どもの視野を大きく広げます。
地域での関わりを通じて、思いやりや柔軟な対応力が磨かれ、社会の中で協働する力が深まっていきますよ。
協働性を育む方法:④失敗を責めず見守り成功までサポートする
協働性を育てる上で、親の「見守る姿勢」は極めて重要です。



協働の場面では、必ずしもすべてがうまくいくわけではありません。
意見が対立したり、失敗したりすることもあります。
そんな時、親が「なんでできないの!」と責めてしまうと、子どもは「失敗するのが怖い」「協力するのは大変だ」と感じ、協働を避けるようになってしまいます。
一方、親が「失敗しても大丈夫」「どうすればうまくいくか一緒に考えよう」という姿勢で見守ることで、子どもは「失敗は学びのチャンス」と捉え、挑戦し続けることができます。



実践のコツがあれば知りたいです。
- 過程を褒める:「最後まで頑張ったね」「友達と協力してたね」と努力を評価
- 一緒に振り返る:「どこが難しかった?」「次はどうしようか?」と話す
- 親の失敗談を話す:失敗が誰にでもあることを伝える
- すぐに手を出さない:考える時間を与える
失敗を恐れずに挑戦できる環境こそ、協働性を育てるうえで大切です。
結果よりも努力や工夫の過程を認めることで、子どもは自分で考え、仲間と支え合う力を伸ばしていきます。
協働性を育む方法:⑤親自身が協働の手本を見せる
子どもは、親の姿を見て育ちます。
親が協働する姿を見せることは、最も効果的な教育です。
なぜ親の手本が重要なのかというと、「こうしなさい」と言葉で教えるよりも、実際に親が協働している姿を見せる方が、子どもは自然と協働性を学ぶからです。
「お父さんとお母さんが協力している」「お母さんが近所の人と助け合っている」という姿を見ることで、子どもは「協働は当たり前のこと」と認識します。



心理学の「社会的学習理論」によれば、子どもの行動の多くは、周囲の大人(特に親)の行動を観察して学習されると言われています。



家庭でできる手本の示し方を知りたいです。
- 夫婦で家事を分担する姿を見せる:料理、掃除、育児など、夫婦が協力して家事を分担する姿を見せる。
- 助けを求めることや感謝を伝える習慣を持つ:これ重いから、一緒に持ってくれる?」「疲れたから、代わりにお願いできる?」と家族に助けを求める姿を見せる。
地域での手本の見せ方も大事です。
- 近所の人に挨拶をする:「おはようございます」「いつもありがとうございます」と近所の人と挨拶する姿を見せることで、地域とのつながりの大切さを伝える。
- PTAや地域行事に参加する:参加する姿を見せることで、「大人も協働している」と子どもは学ぶ。
- 困っている人を自然に助ける:親が他者を助ける姿を見せることで、子どもは「困っている人を助けるのは当たり前」と感じる。
親が協力し合う姿を見せることが、何よりの教育になります。
言葉よりも行動で「協働とはこういうものだ」と伝えることで、子どもは自然とその価値を学んでいきます。
協働性を育む方法:⑥家族以外の人と交流する機会を増やす


家族以外の人々と関わる経験は、子どもの協働性を大きく広げます。



なぜ家族以外との交流が重要なんですか。
家族は、お互いの性格や考え方を理解しているため、協働がしやすい環境です。
しかし、社会に出ると、初めて会う人や、考え方が全く違う人とも協働しなければなりません。
家族以外の人と交流する経験を積むことで、「どんな人とでも協力できる」柔軟性が育ちます。



友達の家族との交流であれば、友達家族と一緒にキャンプやバーベキューしたり、友達のお母さんと一緒に料理を作ってみるのがいいかもしれません。
地域の人々との交流は、 近所の人と挨拶を交わしたり、地域のイベントに参加する等です。
親が「こちらは○○さんだよ」と橋渡し役をし、交流後に「どんな話をしたの?」と振り返ることで、学びが深まります。
年齢や背景が異なる人との関わりを意識的に作りましょう。
小学5年生のナナちゃんは、地域の「異世代交流プログラム」に参加しています。
このプログラムでは、小学生、中学生、高校生、大学生、そして地域のお年寄りが一緒に活動します。
ナナちゃんは、「お姉さんたちは頼りになる」「おじいちゃんたちは面白い話をしてくれる」と、様々な年齢の人と協働する楽しさを感じてるようです。
この経験を通じて、「年齢が違っても、みんなで協力すれば楽しいことができる」と学んでいます。
家庭の外での人間関係は、協働の幅を広げる大切な経験です。
異なる価値観や考え方に触れることで、子どもは柔軟な思考とコミュニケーション力を育んでいきます。
協働性を育む方法:⑦映画や絵本で感情表現を学ばせる
協働には「相手の気持ちを理解する力(共感力)」が欠かせません。
映画や絵本は、登場人物の感情や協力の場面を通して、子どもの共感力を高めます。
映画や絵本の登場人物は、様々な感情を表現しますよね。
その中で、喜び、悲しみ、怒り、困惑など、多様な感情に触れることで、子どもは「人にはいろいろな気持ちがある」と理解します。
また、登場人物が協力して問題を解決する場面を見ることで、「協働の大切さ」を自然と学びます。



心理学の研究では、物語を通じて感情を学んだ子どもは、実生活でも他者の感情を理解する能力が高いことが報告されていますよ。
おすすめの作品はこちらです。
- 幼児期におすすめの絵本:「おおきなかぶ」「スイミー」「14ひきシリーズ」
- 学童期におすすめの映画:「トイ・ストーリー」「となりのトトロ」「リメンバー・ミー」
子どもと一緒に観たり読んだりして、「どのシーンが印象に残った?」「登場人物はどんな気持ちだったかな?」と話し合いましょう。
「ここで、みんなが協力したから成功したんだね」と協働の場面を指摘することで、子どもは協働の大切さを意識します。



協働の場面を一緒に振り返ることで、協力の大切さが心に残りますよ。
物語を通じて他者の気持ちを理解する経験は、協働の根底にある「共感力」を育てます。
感情を想像する力が高まるほど、相手を尊重しながら協力する姿勢が身につきます。
協働性を育む方法:⑧子どもの意見を尊重し対話する時間を作る


協働性を育てるには、「自分の意見を持つ」「意見を適切に伝える」「他者の意見を聞く」というスキルが必要です。
これらは、家庭での対話を通じて育ちます。
なぜ対話が協働性を育てるのかというと、協働の場面では、常に意見交換が行われるからです。
「自分はこう思う」「あなたの意見も分かる」「じゃあ、こうしよう」という対話のプロセスを、家庭で日常的に経験することで、子どもは自然と対話のスキルを身につけます。
また、親が子どもの意見を真剣に聞く姿勢を見せることで、子どもは「自分の意見には価値がある」と感じ、自己肯定感も高まります。



どのようにしたらいいですか。
まず、子どもの意見を最後まで聞きましょう。
途中で遮らず、子どもが話し終わるまで聞きます。



「そうなんだね」「それでどうなったの?」と相槌を打ちながら聞くことで、子どもは「話を聞いてもらえている」と感じます。
「なぜそう思うの?」と理由を聞くことも大事です。
子どもの意見に対して、「なぜそう思うの?」と理由を聞くことで、子どもは自分の考えを深める練習ができます。
そのとき、一方的に子どもの意見を聞くだけでなく、「お母さんはこう思うよ」と親の意見も伝えることで、「意見は人それぞれ違う」と学びます。
一緒に決めるということも忘れないでください。
「今度の休みはどこに行く?」「夕食は何にする?」など、家族のことを一緒に決める経験を積むことで、「話し合って決める」協働の基本を学びます。
対話の時間を確保することも重要です。
忙しい日常の中でも、「夕食の時間」「お風呂の時間」「寝る前の時間」など、決まった時間に対話する習慣を作るようにしましょう。



これなら実践できそうです!
子どもの意見を尊重し対話する時間を作ることで身につく可能性の高いスキルがこちらです。
- 自分の考えを言語化する力
- 相手の意見を理解する力
- 意見が違っても尊重し合う姿勢
- 話し合いを通じて合意を形成する力
これらのスキルは、学校でのグループワーク、将来の職場、家庭生活など、あらゆる場面で役立ちます。



日々の対話は、協働の第一歩です。
親が子どもの考えを尊重し、共に話し合うことで、「自分の意見が受け入れられる安心感」と「他者と意見を交わす力」が自然と育まれていきます。
年齢別・協働性を高める親の関わり方


子どもの協働性は、年齢や発達段階によって育ち方が大きく異なるのは知っていますか。
3歳の子どもにとっての「協力」は、親と一緒に遊ぶ中で「楽しい!」と感じることから始まり、学童期に入ると「友達と意見を出し合って形にする経験」へと発展していきます。
さらに高学年になると、仲間の意見を尊重しながら自分の考えを伝える「成熟した協働力」が求められるようになります。
そのため、親は子どもの発達段階に合わせてサポートの仕方を変えることが大切です。



ここでは、年齢ごとに意識したい関わり方のポイントと、協働性を自然に伸ばす実践方法を紹介します。
3〜5歳は遊びの中で「一緒にやる」楽しさを教える


幼児期は、協働性の基礎を築く重要な時期です。
この時期の子どもは、「自分でやりたい」という自我が芽生える一方で、「一緒にやると楽しい」という協働の喜びも感じ始めます。
3〜5歳頃の子どもは、少しずつ自己中心的な思考から抜け出し、周囲の人の存在を意識できるようになります。
遊びの中で「順番」や「ルール」を理解し始め、他者と関わる力が育ち始める時期です。
また、簡単な役割分担にも興味を示し、「自分の役目」を果たすことに喜びを感じるようになります。



おすすめの関わり方も教えてください。
- ごっこ遊びを一緒に楽しむ
「お店屋さんごっこ」など、役割を分けて遊ぶことで協働の基礎を学びます。 - 共同作業を経験させる
積み木で一緒に建物を作るなど、協力して成果を出す楽しさを感じさせましょう。 - 感謝のやり取りを習慣にする
「ありがとう」「どういたしまして」と言葉で伝えることで、協働の心が育ちます。 - 順番を待つ練習をする
ブランコや滑り台などで「順番」を守る体験を積ませましょう。 - 友達と遊ぶ機会を増やす
公園や児童館などで、他の子どもと自然に関わる環境を作ることも効果的です。
注意点として、無理に協力させるのではなく、「できた!」「楽しい!」という体験を重ねることが大切です。
親が楽しそうに関わる姿を見せることで、子どもは自然と協働の喜びを学んでいきます。



この時期は、結果よりも「一緒にやる楽しさ」を感じさせることが何よりも重要です。
遊びを通して自然に協働の基礎が育っていきます。
6〜8歳は失敗を見守り成功体験を積み重ねる
学童期前半は、協働性を実践的に育てる時期です。
学校生活が始まり、友達との協働の機会が増えます。
この時期の子どもは、論理的に考える力が少しずつ育ち、相手の気持ちや立場を理解できるようになっていく時期です。
友達との関係の中で、ルールを守る大切さや、協力しながら目標を達成する喜びを学び始めます。



おすすめの関わり方はこちらです。
- グループ活動に参加させる
スポーツや音楽教室などで、仲間と協力して成果を出す経験を積ませましょう。 - 失敗を成長のきっかけにする
うまくいかなかった経験も「どうすれば良くなるか」を考える材料にします。 - 家庭で役割を与える
掃除や料理など、小さな責任を任せて達成感を味わわせましょう。 - 人間関係の悩みを聞く
友達とのトラブルも、解決策を一緒に考えることで学びに変わります。 - 成功を共に喜ぶ
結果だけでなく「みんなで協力できた」という過程を褒めましょう。
注意点は、比較や口出しを避け、子ども自身が考える力を信じて見守る姿勢が大切です。
具体例も挙げますのでご覧ください。
小学2年生のエミちゃんは、クラスで壁新聞を作るグループに入りました。
しかし、意見が合わず、涙を流して帰ってきたんです。
お母さんは「大変だったね」と気持ちを受け止めた上で、「どうすればみんなの意見を活かせるかな?」と一緒に考えました。
翌日、エミちゃんは「それぞれのアイデアを少しずつ取り入れる」という提案をし、グループは無事に壁新聞を完成させることができました。
この経験を通じて、エミちゃんは「意見が違っても、話し合えば解決できる」ことを学んだのです。



失敗を恐れず挑戦できる環境を整えることが、協働性を一段と伸ばす鍵になります。
9〜12歳は自主性を尊重しながらサポートする
高学年になると、自分の意見や他者の立場を理解しながら行動する力が育ち、より高度な協働が可能になります。
自分の意見を持ちながらも、周囲と調和をとる力が伸び、リーダーシップや責任感が芽生える時期です。
また、ルールや約束を守る意識が高まり、協力と競争のバランスを学びながら、主体的に行動できるようになります。



おすすめの関わり方を教えてください。
- 自主性を尊重する
「どう思う?」と問いかけ、子どもが自ら考える機会を増やします。 - 複雑なプロジェクトに参加させる
行事や地域活動などを通じて、長期的な協働を経験させましょう。 - リーダーシップの練習をさせる
「みんなの意見をまとめる役割」を任せ、サポート役に回ります。 - 多様な価値観に触れさせる
本や映画、地域交流を通じて、異なる考え方を理解する柔軟さを育てましょう。 - 将来について話す
「協働できる力が社会でどう活きるか」を考える機会を作ります。
注意しなければいけないことは、過保護にならず、信頼して任せることです。
失敗も含めて成長のプロセスとして受け止めましょう。



自ら考え、他者と協力して行動できる力を育むことで、思春期以降にもつながる「主体的な協働性」が身につきます。
協働性を育てる上で親が気をつけたい5つのこと
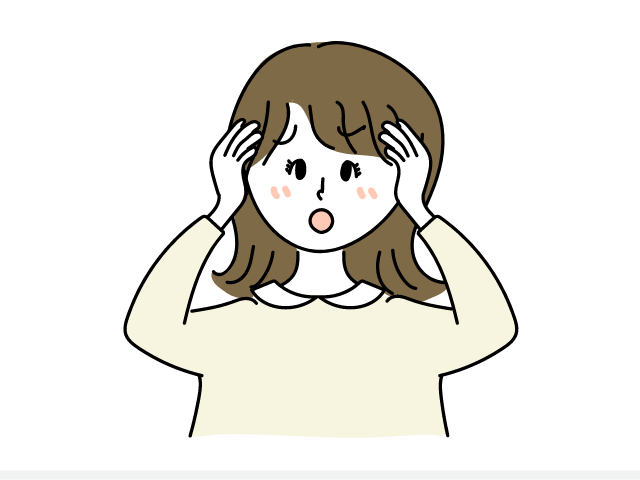
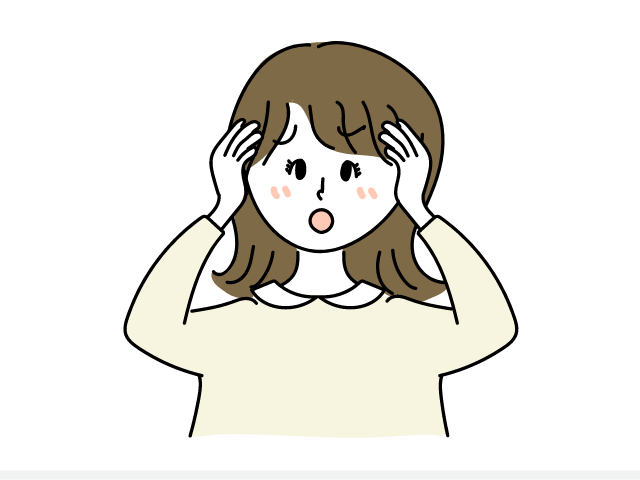
子どもの協働性を育てるうえで、親の関わり方は非常に重要です。
どんなに良い環境や教材を与えても、親の関わり方ひとつで子どもの意欲や自信は大きく変わります。
特に協働性は、知識のように「教えて身につく」ものではなく、日々の関わりや経験の中で少しずつ育まれる力です。
しかし、良かれと思ってかけた一言や、他の子と比べた何気ない態度が、子どもの心にプレッシャーや苦手意識を生むこともあります。



ここでは、親が陥りやすい5つの落とし穴と、それを避けながら協働性を自然に伸ばすための関わり方を具体的に解説します。
今日から意識を少し変えるだけで、子どもが「人と一緒に頑張るって楽しい!」と感じられるようになりますよ。
まずは全体をひと目で把握できるように、表にしましたのでご覧ください。
| 注意点 | 内容のポイント | 親ができること |
|---|---|---|
| ① 過度な期待をかけずペースを尊重 | 子どもの発達には個人差がある。 焦らず見守る姿勢が大切。 | 小さな成長を認め、比較を避ける |
| ② 他の子と比較せず個性を認める | 比較は自己肯定感を下げる原因に。 | 子どもの「得意」や「タイプ」を肯定する |
| ③ 結果より過程を褒める | 「できた」より「どう頑張ったか」を重視する。 | 努力・工夫・協力の姿勢を評価する |
| ④ 失敗を否定的に捉えない | 失敗は学びと成長のチャンス。 | 一緒に振り返り、前向きに支える |
| ⑤ 協働を強制せず自然に促す | 無理に関わらせると逆効果。 | 子どもの興味を起点に自然な協働を導く |



それでは、更に詳しく見ていきましょう。
注意点:①過度な期待をかけず子どものペースを尊重する
協働性の大切さを理解した親ほど、「早く身につけさせたい」と焦ってしまうことがあります。
しかし、過度な期待は逆効果です。



焦ってしまう気持ちがわかります。
どうして、過度な期待が良くないのでしょうか。
子どもの発達には個人差がありますよね。
すぐに友達と仲良くできる子もいれば、時間がかかる子もいます。
親が「なんでできないの!」「もっと頑張りなさい」とプレッシャーをかけると、子どもは「協働=苦しいもの」と感じ、むしろ協働を避けるようになってしまいます。



発達心理学の研究では、親からの過度なプレッシャーを感じている子どもは、自己肯定感が低く、社交不安のリスクが高いことが報告されているんです。
それでは、実践のコツをお伝えします。
小さな進歩を丁寧に認めることが、子どものやる気を育てることを覚えておいてください。
「今日は友達に声をかけられたね」といった言葉がけが、自信につながります。
また、他の子と比べるのではなく、その子自身の成長に目を向けましょう。
焦らず見守る姿勢が、安心感を与え、自然な成長を促します。
得意なことから始めることで「できた!」という成功体験が積み重なり、協働への意欲が生まれていきます。



子どものペースを尊重し、焦らず見守ることが協働性の第一歩になりますよ!
注意点:②他の子と比較せず個性を認める
「隣の芝生は青く見える」という言葉があるように、他の子と比較してしまうことは親の自然な心理です。
しかし、比較は子どもの成長を妨げます。



これは気を付けないといけないことですよね。
ただ、知っておきたいことの一つですが、どうして比較をすることは良くないのでしょうか。
なぜ比較が良くないのかというと、子どもには一人ひとり個性があります。
社交的な子もいれば、内向的な子もいますよね。
そして、リーダーシップを発揮するのが得意な子もいれば、サポート役が得意な子もいます。
比較することで、子どもは「自分はダメな子だ」と感じ、自己肯定感が低下するといわれているからです。
親から頻繁に他の子と比較された子どもは、自己肯定感が低く、将来的に心理的な問題を抱えるリスクが高いともいわれています。



実践のコツが知りたいです。
他の子と比べるのではなく、「以前のその子」と比較して成長を見守ることが大切です。
「3ヶ月前よりできるようになったね」といった言葉が、努力の過程を肯定します。
また、「慎重なのは○○ちゃんの良いところだよ」と個性を肯定することで、子どもは安心して自分らしく行動できるようになります。



親自身も「社交的であるべき」といった価値観を見直し、多様な強みを認める姿勢を持ちましょう。
具体例をみてください。
小学3年生のショウタくんは、クラスで目立つタイプではなく、いつも友達のサポート役でした。
お母さんは「もっとリーダーシップを発揮してほしい」と思っていましたが、先生から「ショウタくんは、困っている友達に気づいて助けてあげる優しい子です」と言われ、考えが変わりました。
「サポート役も立派な協働性なんだ」と理解し、ショウタくんの個性を認めるようになりました。
比べるのではなく“その子らしさ”を認めることが、協働性を伸ばす土台になります。
注意点:③結果より過程を褒める


協働性を育てる上で、「結果」ではなく「過程」を褒めることが極めて重要です。



なぜ過程を褒めるべきなのでしょうか。
「優勝したからすごい」「一番だったから偉い」という結果重視の褒め方は、子どもに「結果を出さなければ価値がない」というメッセージとして伝わってしまいます。
これでは、失敗を恐れて挑戦しなくなったり、結果が出ない時に自己否定したりする可能性が高いです。
一方、「最後まで諦めずに頑張ったね」「友達と協力しようとしていたね」という過程を褒めることで、子どもは「努力や協力すること自体に価値がある」と理解します。



実践のコツをお伝えします。
「一番になったね」よりも「最後まで頑張ったね」といった声かけが、子どもの挑戦意欲を伸ばすので、試してみてください。
頑張りや工夫といった過程を具体的に褒めることで、「努力すること自体に価値がある」と理解できるようになります。
失敗しても「挑戦したことがすごい」と伝えれば、失敗を恐れず前向きに挑戦できるようになります。
協力しようとする姿勢を評価することも、協働性を育てるうえで欠かせません。



結果よりも過程を認めることで、子どもは他者と協力しながら学ぶ力を育てていきます。
注意点:④子どもの失敗を否定的に捉えない
協働の場面では、必ず失敗があります。
親が失敗を否定的に捉えると、子どもは挑戦することを恐れるようになります。



それは困りますね。
なぜ失敗を肯定的に捉えるべきなのでしょうか。
失敗は、成長のための貴重な学びの機会です。子どもが失敗から学ぶことで、問題解決力、回復力(レジリエンス)、柔軟性が育ちます。
失敗を「学びの機会」と捉える家庭で育った子どもは、失敗を「恥」と捉える家庭で育った子どもに比べて、将来の成功率が高いといわれています。



どのように対応したらいいのか気になりますよね。
下記を実践してみてください。
失敗を責めるのではなく、まず「大変だったね」と気持ちを受け止めましょう。
その上で、「次はどうすればうまくいくかな?」と一緒に振り返ると、失敗を学びに変えられます。
親が自分の失敗談を話すのも効果的です。
「失敗は誰にでもある」と伝えることで、子どもは安心して再挑戦できます。
「挑戦したこと自体がすばらしい」と肯定する姿勢が、子どもの耐久力などを育てます。



失敗を恐れない環境が、子どもの挑戦心と協働性の成長を後押ししますよ。
注意点:⑤協働を強制せず自然な形で促す
協働性の大切さを理解している親ほど、「協働させなければ」と焦り、強制してしまうことがあります。
しかし、強制は逆効果です。
なぜ強制が良くないのかを簡潔にお伝えします。
「友達と遊びなさい」「グループに入りなさい」と強制すると、子どもは「協働=嫌なもの」と感じるケースが多いです。
協働は、本来楽しいものであり、自然に生まれるものです。親が無理に協働させようとすると、子どもは協働そのものを嫌いになってしまいます。



外部からの強制ではなく、内発的な動機(自分からやりたいと思う気持ち)によって行動する方が、学習効果が高く、持続性も高いといわれていますよ。
それでは、実践のコツをお伝えします。
協働を無理に押しつけるのではなく、子どもの興味を起点に自然な関わりを作りましょう。
たとえば、「恐竜が好きな友達がいるよ」といったさりげない提案が、子どもに「話してみたい」という気持ちを芽生えさせます。
「友達と遊びたい」「一人で遊びたい」という子どもの選択を尊重しながら、協働しやすい環境を整えることが大切です。
親が焦らず待つことで、子ども自身の「やってみたい」が育ち、自然と協働の楽しさに気づいていきます。
内向的なレンくんは、いつも一人で本を読んでいました。
お母さんは「友達と遊んだ方がいいのでは」と心配していましたが、無理に友達と遊ばせることはしませんでした。
ある日、レンくんが興味を持っている恐竜について、同じように恐竜好きの友達がいることを知り、「一緒に恐竜の図鑑を見てみる?」と提案したんです。
レンくんは自分から「うん!」と答え、友達と楽しく恐竜について語り合いました。
このように、子どもの興味を起点に、自然な形で協働を促すことが大切です。
協働性を高めるおすすめの習い事10選


家庭での声かけや遊びの工夫も大切ですが、協働性をさらに伸ばすには、習い事を通じて多様な人と関わる経験がとても効果的です。
グループでの活動や共同作業を伴う習い事では、「自分の意見を伝える」「相手の考えを聞く」「協力して目標を達成する」といった力が自然と身につきます。
また、年齢や性格の異なる仲間と関わることで、思いやりや責任感、チームで行動する力が育ち、学校生活や将来の社会生活にも大きく役立ちます。



ここでは、協働性を高めるのに特におすすめの習い事を10種類ピックアップし、それぞれの特徴と得られる効果をわかりやすく紹介します。
チームスポーツ:役割分担と協力を実践的に学ぶ


サッカー、野球、バスケットボール、バレーボールなどのチームスポーツは、協働性を育てる最も効果的な習い事の一つです。
チームスポーツでは、一人ひとりがポジションという役割を持ち、チーム全体で勝利を目指します。
「自分の役割を果たす」「仲間と連携する」「チームのために行動する」という協働の基本を、実践を通じて学びます。
また、試合という明確な目標があるため、「目標達成のために協力する」という協働の本質を体験できるのです。



具体的な効果についてもお伝えしますね。
- 役割意識の育成:自分のポジションの責任を理解し、役割を果たす力が育つ
- コミュニケーション能力:プレー中の声かけ、作戦会議など、常にコミュニケーションが必要
- リーダーシップとフォロワーシップ:キャプテンやベテラン選手からリーダーシップを、新人選手からフォロワーシップを学ぶ
- 勝敗を通じた学び:勝った時の喜びを仲間と分かち合い、負けた時は一緒に悔しさを乗り越える
幼児期(3〜5歳)であれば、親子サッカー教室など、遊び感覚で参加できるものがおすすめです。
学童期(6〜12歳)は、本格的なチームスポーツで学ぶ方が多いです。
選ぶ際のポイントは、勝利至上主義ではなく、「楽しむこと」「成長すること」を重視するチームを選ぶようにしてください。
コーチが子どもの個性を尊重し、一人ひとりの成長を見守る姿勢があるか確認しましょう。
なにより、チームの雰囲気が良く、子どもが「行きたい」と思えるかが大事です。



保護者の声を紹介します。
息子はサッカーを始めてから、『チームのために』という意識が芽生えました。
家でも『家族のために』と自分から手伝いをするようになり、協働性が育っていると感じます。
チームスポーツは、協働の基本である「役割を理解し、仲間と力を合わせる力」を育てます。
勝ち負けを通して学ぶ経験は、子どもが人との関わり方を深く理解する大切なステップになりますよ。
ダンス:仲間と息を合わせる一体感を体験する


バレエ、ヒップホップ、ジャズダンスなど、ダンスは協働性を育てる優れた習い事です。
ダンスでは、グループで一つの作品を作り上げます。
全員の動きが揃っていないと美しく見えないため、「仲間と息を合わせる」「相手の動きを感じ取る」という協働の感覚が自然と身につきます。



また、発表会という明確な目標に向かって、仲間と一緒に練習を重ねることで、「協力して一つのものを作り上げる」達成感を味わえますよね。
具体的な効果はこちらです。
- 一体感の体験:全員の動きが揃った時の一体感は、協働の喜びそのもの
- 相手を感じ取る力:隣の人の動きを感じながら踊ることで、他者への意識が高まる
- 表現力とコミュニケーション:身体表現を通じて、非言語コミュニケーション能力が育つ
- 忍耐力と協調性:何度も練習を重ねる中で、忍耐力と協調性が育つ
幼児期であれば、リトミックや幼児ダンス、学童期は本格的なダンスレッスンがおすすめです。
選ぶ際は、個人の技術向上だけでなく、グループでの作品作りを重視する教室を選ぶようにしてください。
発表会があり、目標に向かって協力する経験ができるかも大事です。
先生が子どもの個性を活かしながら、全体の調和も大切にしているかどうかも確認しましょう。



ダンスは、仲間と動きを合わせる中で「感じ取る力」と「表現する力」を同時に育てます。
音やリズムに合わせて協力する経験が、子どものコミュニケーション力を自然に高めてくれますよ。
合唱団・ミュージカル:表現力と協調性を同時に育む


合唱団やミュージカルは、音楽と演劇を通じて協働性を育てます。



なぜ協働性が育つのか知りたいです。
合唱では、一人ひとりの声が調和して初めて美しいハーモニーが生まれます。
「自分の声を出しながら、他の人の声も聞く」というバランス感覚が、協働の本質です。



ミュージカルでは、歌、ダンス、演技という複数の要素を組み合わせて一つの作品を作ります。
俳優、歌手、ダンサー、裏方など、様々な役割があり、それぞれが協力して初めて作品が完成します。
具体的な効果も確認しましょう。
- ハーモニーの体験:自分の声と他者の声が調和する喜びを体験
- 役割の多様性:主役、脇役、裏方など、様々な役割があることを学ぶ
- 表現力:音楽や演技を通じて、豊かな表現力が育つ
- 達成感:公演という大きな目標に向かって協力し、達成感を味わう
幼児期は、音楽遊びや簡単な合唱、学童期は本格的な合唱団やミュージカル劇団がおすすめです。
選ぶ際のポイントは、「定期的に発表の機会があるか」「子どもの年齢や経験に応じた役割が与えられるか」がポイントです。



技術だけでなく、「みんなで作り上げる」過程を大切にしているか
も確認した方がいいかもしれません。
合唱やミュージカルは、個々の表現を調和させながら一つの作品を作り上げる喜びを教えてくれます。
多様な役割の中で協力する経験が、子どもの社会的な成長につながります。
ボーイスカウト:多様な年齢層と協働する力がつく


ボーイスカウト(ガールスカウト)は、協働性を育てるために特別に設計された活動です。
ボーイスカウトでは、異なる年齢の子どもたちが一緒に活動し、年上の子は年下の子の面倒を見ながら、年下の子は年上から多くを学ぶという、自然な協働の関係が生まれます。
また、キャンプ、ハイキング、奉仕活動など、様々な活動を通じて、実践的な協働スキルを学びます。



ボーイスカウト(ガールスカウト)は一番気になる習い事でした。
具体的な効果も知りたいです!
- 異年齢交流:様々な年齢の人と協働する力が育つ
- リーダーシップ:年下の子どもの面倒を見ることで、リーダーシップが育つ
- 実践的なスキル:キャンプやハイキングを通じて、実生活で役立つスキルを協働で学ぶ
- 奉仕の精神:地域奉仕活動を通じて、社会貢献の意識が育つ
団によって異なりますが、小学1年生から参加可能なケースが多いです。
選ぶ際のポイントは、活動内容が多様なため、子どもの興味に合っているかを見極めることが大事です。
「リーダー(指導者)が子どもの自主性を尊重しているか」「保護者の関わり方(サポートの程度)が家庭の状況に合っているか」も確認しましょう。



保護者の意見も見てみましょう。
娘はボーイスカウトで、年上のお姉さんたちに憧れ、年下の子どもたちの面倒を見るようになりました。異年齢の中で協働する力は、学校だけでは得られない貴重な経験でした。
ボーイスカウトは、年齢を超えた協働を通して、思いやりやリーダーシップを育てる貴重な場です。
実体験を通して「人のために行動する力」を学べるのが大きな魅力です。
料理教室:共同作業で達成感を味わう
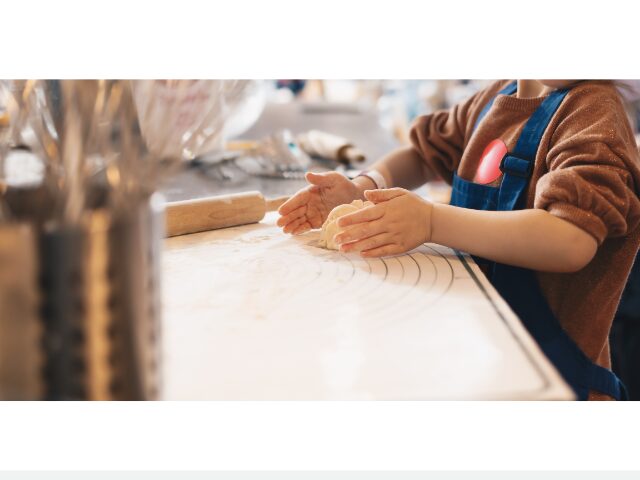
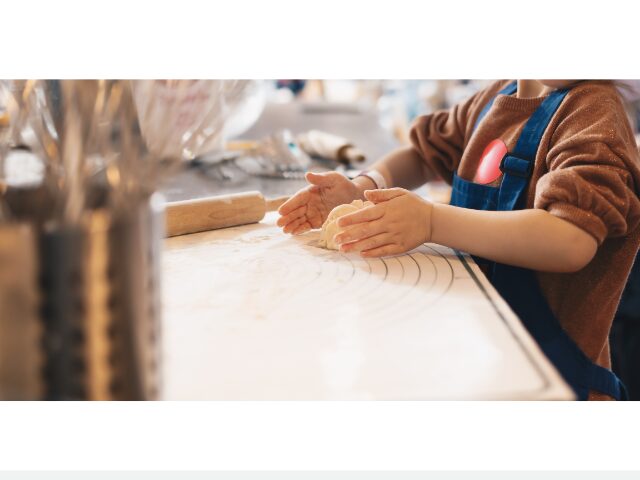
子ども向けの料理教室は、協働性を育てる実践的な場です。
料理は、材料の準備、調理、盛り付け、片付けという一連の作業を、役割分担しながら進めます。
「誰が何を担当するか」を話し合い、協力して一つの料理を完成させることで、協働の基本を学びます。



また、料理という具体的な成果物があるため、「協力した結果」が目に見えて分かり、達成感を味わいやすいのも特徴です。
具体的な効果はこちらになります。
- 役割分担:誰が何をするかを話し合い、役割を分担する力が育つ
- コミュニケーション:「次は何をする?」「これ持ってて」など、常にコミュニケーションが必要
- 達成感:協力して作った料理を一緒に食べる喜びは格別
- 生活スキル:料理という実生活で役立つスキルも身につく
幼児期は親子料理教室、学童期は子ども向け料理教室がおすすめです。
選ぶ際は、グループで一つの料理を作る形式か、個人で作る形式か確認することが大事です。



安全対策がしっかりしているかも気になります。



そうですよね。
あとは、子どもの年齢や経験に応じたメニューなのかも選ぶ際のポイントになりますよ。
料理教室では、協力しながら一つの料理を完成させる達成感が得られます。
実生活にもつながる協働の力を、楽しみながら身につけることができます。
科学実験教室:仲間と試行錯誤しながら学ぶ


科学実験教室は、知的好奇心を満たしながら協働性も育てられる習い事です。
科学実験では、グループで仮説を立て、実験し、結果を考察するというプロセスを踏みます。
「どうすればうまくいくか」を仲間と一緒に考え、試行錯誤を重ねる中で、協働的な問題解決力が育っていきます。



さらに、実験という「正解が一つではない課題」に取り組むことで、異なる意見を受け入れ、他者の考えを尊重する姿勢も身につけられるでしょう。
- 協働的な問題解決:仲間と一緒に考え、試行錯誤する力が育つ
- 多様な視点:一つの課題に対して、様々なアプローチがあることを学ぶ
- 論理的思考:仮説→実験→考察というプロセスを通じて、論理的思考が育つ
- 知的好奇心:科学への興味が高まり、学習意欲も向上



科学実験教室は幼児期でも大丈夫なんですか。



幼児期は簡単な科学遊びがおすすめです。
学童期になってから、本格的な科学実験をするのが理想です。
選ぶ際のポイントは、グループで実験を行う形式かを確認することが重要になります。
子どもの「なぜ?」を大切にし、自分で考えさせる指導方針かも大事です。



最も重要なのが、安全対策がしっかりしているか
どうかです。
必ず確認するようにしましょう。
科学実験教室は、「考える力」と「協力して解決する力」を同時に育てます。
仲間と意見を交わしながら挑戦する経験が、子どもの探究心と柔軟な思考を引き出します。
キッズ英会話教室:グループ活動でコミュニケーション力を磨く


グループレッスン形式のキッズ英会話教室は、言語学習と協働性の育成を同時に行えます。
英会話教室では、ゲーム、ロールプレイ、グループディスカッションなど、仲間と一緒に英語を使う活動が中心です。
「英語で伝える」「相手の英語を理解する」というコミュニケーションを通じて、協働性が育ちます。
また、英語という共通の目標に向かって、仲間と一緒に学ぶことで、「協力して学ぶ」楽しさを体験できます。
- コミュニケーション能力:英語でのコミュニケーションを通じて、伝える力・聞く力が育つ
- 多様性の理解:外国人講師や異文化に触れることで、多様性を受け入れる力が育つ
- 協働的な学習:仲間と一緒に英語を学ぶことで、協働学習の楽しさを体験
- グローバル意識:世界とつながる意識が育つ



幼児期であれば、歌やゲームを中心とした英語遊び
が多いです。
学童期から本格的なレッスンを行う教室が多いということがわかっています。
個人レッスンでは協働性は育ちにくいため、グループレッスン形式かの確認は大事です。
ゲームやグループ活動を取り入れた、楽しく学べるカリキュラムであるかどうか、講師が子どもの発言を引き出し、コミュニケーションを促す指導をしているかも確認しましょう。
息子は英会話教室で、『言葉が通じなくても、ジェスチャーや表情で伝えられる』ことを学びました。
コミュニケーションの本質を理解したようです。
英会話教室では、言葉の壁を越えて協力し合う体験を通じて、国際的な視野と協働性が育ちます。
仲間と共に学ぶことで、積極的に自分を表現する力も伸ばせます。
演劇・劇団:役割を理解し協力して作品を作る


演劇や劇団活動は、協働性を総合的に育てる習い事です。
演劇では、俳優、演出、照明、音響、衣装、大道具など、様々な役割があります。
一人ひとりが自分の役割を果たし、全員が協力して初めて一つの作品が完成するのです。
その過程で、「自分の役割の重要性」と「全体の中での自分の位置づけ」を同時に理解できるようになります。
さらに、公演という明確な目標に向かって長期間にわたり協働することで、忍耐力や責任感も養われていきます。
- 役割の多様性:様々な役割があり、それぞれが重要であることを学ぶ
- 表現力:演技を通じて、豊かな表現力が育つ
- 長期的な協働:数ヶ月にわたって協力することで、持続的な協働力が育つ
- 達成感:公演の成功という大きな達成感を仲間と共有



幼児期であれば簡単な劇遊びがおすすめです。
本格的な劇団活動は学童期からが良いでしょう。
選ぶ際には、定期的に公演があるかどうかを確認しておいた方がいいです。
主役だけでなく、脇役や裏方も大切にする雰囲気かどうかも大事です。
子どもの個性を活かした配役や役割分担をしているかも確認してください。



演劇活動は、役割分担と協力の大切さをリアルに体験できる学びの場です。
一人ひとりの努力が作品を作り上げるという実感が、子どもの責任感と協働力を深めます。
ロボット・プログラミング教室:チームで課題解決に取り組む
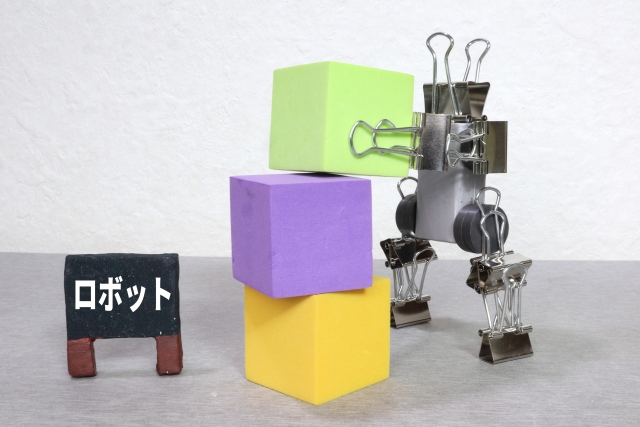
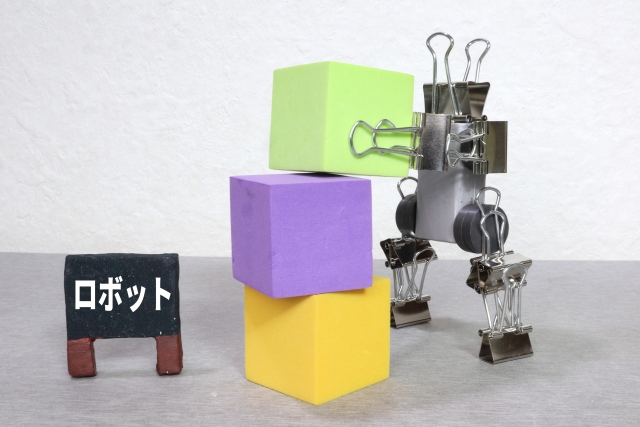
ロボット・プログラミング教室は、21世紀のスキルと協働性を同時に育てる学びの場です。
ロボット・プログラミングでは、グループで一つのロボットを作り、プログラムを組んで動かしていきます。
「どんなロボットを作るか」「どのように動かすか」を話し合いながら、役割分担(ロボット製作担当、プログラミング担当など)をして取り組むのが特徴です。



さらに、ロボットコンテストなどチームで課題に挑戦する機会も多く、仲間と協力して試行錯誤する中で、協働的な問題解決力が身につきます。
- 協働的な問題解決:複雑な課題をチームで解決する力が育つ
- 役割分担:それぞれの得意分野を活かした役割分担を学ぶ
- 論理的思考:プログラミングを通じて、論理的思考が育つ
- 21世紀のスキル:プログラミングという将来役立つスキルも身につく
ロボット・プログラミング教室のおすすめの年齢は、学童期です。
ビジュアルプログラミングから始めることになります。
選ぶ際のポイントは、グループで取り組む形式かどうかを見極めましょう。
コンテストなど、目標に向かって協働する機会があるかどうか、子どもの創造性を尊重し、試行錯誤を促す指導方針かもあわせて確認してください。
息子はロボット教室で、『一人では解決できない問題も、友達と協力すれば解決できる』ことを学びました。
協働の力を実感しているようです。



ロボット・プログラミングは、創造力と協働力を融合させた学びです。
チームで試行錯誤を重ねる過程で、問題解決力と仲間を尊重する姿勢が育ちます。
オーケストラ・吹奏楽:全体のハーモニーを生み出す協働を学ぶ


ヴァイオリン、フルート、打楽器など、オーケストラ・吹奏楽は協働性の究極形を体験できる習い事です。
オーケストラでは、各楽器が自分のパートを完璧に演奏しつつ、全体のハーモニーを作り上げます。
1つの楽器がミスすると全体が崩れるため、「自分の役割を果たす」「他者の音を聴き合わせる」「指揮者の指示に合わせる」という高度な協働スキルが自然と身につきます。



また、定期演奏会という明確な目標に向かって、何ヶ月も仲間と練習を重ねることで、「長期的な協力で大きな成果を生む」達成感を味わえます。
- 全体意識の育成:自分の音が全体にどう影響するかを体感
- 聴き取り力:他者の演奏をリアルタイムで聴き合わせる
- 役割理解:各楽器の強みを活かした分担を実感
- 忍耐力・責任感:長期間の合奏練習で協調性と集中力が育つ
幼児期はリコーダー合奏、学童期は本格的な吹奏楽団や弦楽アンサンブルがおすすめです。
選ぶ際は、個人練習+合奏練習のバランスが取れた教室を選びましょう。
定期演奏会があり、全員で1曲を完成させる経験ができるかも重要です。
先生が各楽器の個性を尊重しつつ、全体の調和を重視しているかどうかも確認しましょう。
オーケストラは、「個の技術」と「全体の調和」を同時に磨く中で、究極の協働力を育てます。



互いの音を聴き合わせる経験が、子どもの「相手を感じ取る力」と「チーム貢献意識」を自然に高めてくれます。
まとめ
いかがでしたか?
協働性とは、仲間と協力しながら共通の目標を達成する力です。
これからの時代、学校でも職場でも、この力がますます重要になります。
- 協働性とはこれからの社会に役立つ能力です!
- 協働性は家でも育む事ができます!
- 協働性は集団でコミュニケーションを取る事ができる習い事を通して高める事もできます!



協働性は一朝一夕に身につくものではありませんが、日々の小さな積み重ねが、やがて大きな力となります。
今日から、できることから始めてみませんか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
