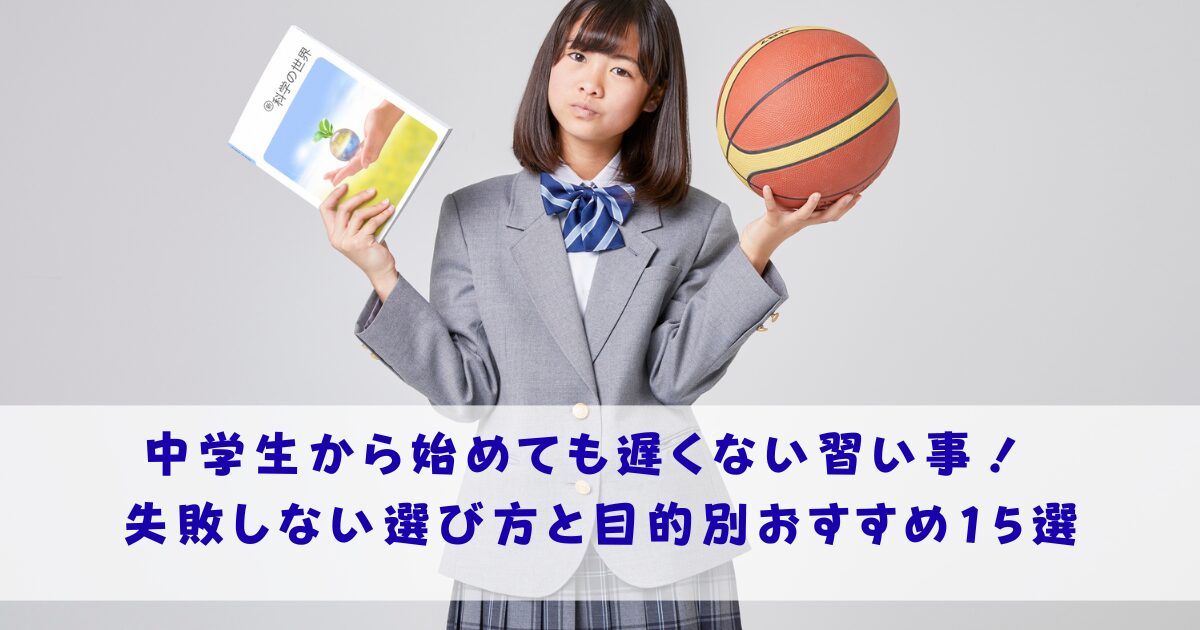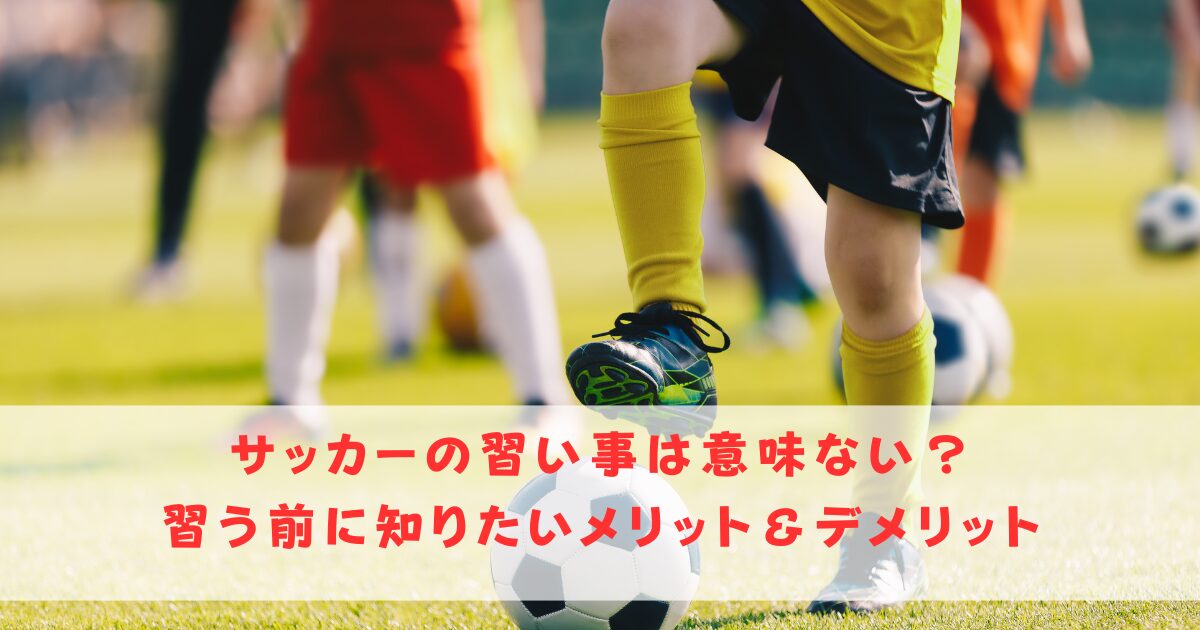中学生になると、部活動や定期テスト、受験準備など、親御さんにとってもお子さんの活動について悩むことが増えてきますね。
特に「もう中学生だし、今から新しい習い事を始めても遅いかな?」と心配されている方もいらっしゃるでしょう。

うちの子、部活に入らないって言ってるけど、毎日スマホばかりで将来が不安…。
今から始めても成果は出ないかもしれないし、どうすればいいかわからないわ。



大丈夫ですよ!
中学生だからこそ、習い事は将来の選択肢を広げる重要な投資になります。
始めるのに遅すぎることは絶対にありません。
- なぜ今、中学生に習い事が必要なのかという社会背景
- 「両立できない」「遅すぎる」といった習い事選びの誤解
- 運動系、将来直結系、文化系の目的別おすすめ習い事15選
- 習い事をやめる時のサインや、親の適切な関わり方
この記事では、「今からでも遅くない中学生の習い事」をテーマに、失敗しない選び方から目的別のおすすめ15選までを徹底解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
中学生にも習い事が求められている3つの社会背景


近ごろ、「中学生から始めても大丈夫な習い事」が人気になっています。
その理由は、学校やまわりの環境が大きく変わってきたからです。
たとえば、「外で体を動かす時間が少なくなったこと」「友だちと直接会っておしゃべりする機会が減ったこと」「あきらめずにがんばる力や、自分で考える力が大切になってきたこと」などがあります。
この章では、3つの背景をわかりやすく解説していきます。
- 部活動の縮小傾向で運動機会が減少している現実
- タブレットやスマホ依存によるコミュニケーション機会の減少
- 非認知能力(集中力・自己表現力)が試される社会への変化



現代の中学生は、かつての学生生活とは異なり、運動や人との交流の機会が減少しているのが現状です。
これは学習面だけでなく、心身の成長にも影響を及ぼしかねません。
だからこそ、習い事で「体を動かす」「人と話す」「自分で考えて工夫する」などの機会をつくることが、とても大切になっています。
とくに、将来の役に立つ「がんばる力」や「自分で考える力」を育てることが、お子さんの可能性を広げる大きなポイントになります。



それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう!
部活動の縮小傾向で運動機会が減少している現実
多くの中学校で、教員の働き方改革や指導者の確保が困難なことから、部活動の活動時間が縮小傾向にあります。
スポーツ庁がまとめた部活動改革の最新報告によると、2023年から2025年度の「改革推進期間」において、部活動の地域移行や地域連携が進められています。
休日の部活動では約54%、平日では約31%の活動が地域スポーツクラブへの移行を予定しており、段階的に部活動の時間は短縮され、中学生の運動機会が確実に減少していることが指摘されています。
これは、お子さんが運動を通じて体力をつけたり、ストレスを発散したりする機会が減っているということです。



たしかに、うちの子の部活も週に1〜2回しかなくて、運動量が足りていない気がします…。



そうですね。
運動不足は体力低下だけでなく、集中力や睡眠の質にも影響します。
この失われた機会を補うのが、習い事の重要な役割になります。
だからこそ、習い事で「しっかり体を動かす時間」をつくることが大切です。
運動の習い事は、学校の部活の時間が少なくなってきた今、その足りない分をおぎなうだけでなく、ずっと大人になってからも楽しめる好きなことを見つけるきっかけにもなります。



また、習い事ではほかの学校の子とも出会えるので、部活とはちがう新しい友だちや仲間ができるチャンスにもなりますよね。
運動の習い事は、体力をつけるだけじゃなく、「集中しやすくなる」「気持ちが安定する」など、心の調子も整えてくれます。
そのおかげで、勉強にも良い影響が出ることがあります。



文武両道という言葉がありますよね!
部活やスポーツを頑張っている子はスケジュール的には忙しいはずですが、限られた時間の中で勉強も頑張ることで集中力が鍛えられるので、成績がアップした子も周りにはたくさんいます!
タブレットやスマホ依存によるコミュニケーション機会の減少


今の中学生は、スマホやタブレットで情報を見たり、友だちとやりとりしたりするのが普通になっていますよね。
でも、こうしたデジタル機器を使う時間が増えるほど、直接会って話す機会が減ってしまうことが心配されています。



うちの子もメッセージアプリでのやり取りは得意ですが、目上の人に話す時は少し自信がなさそうです。



それは多くのお子さんに共通する悩みですね。
画面越しの会話と違って、表情や声のトーンを読み取る訓練が不足しがちです。
対面でのコミュニケーション力、つまり「相手が何を言いたいのか気づく力」や「自分の考えをわかりやすく伝える力」は、将来の面接や大人になってからの人間関係でも、とても大切です。
英会話や、みんなで話し合いながら進めるプログラミング、チームスポーツなどの習い事は、オンラインとはちがう「生きたコミュニケーション」を学べる場所です。



いろいろな年齢や、ちがう学校の子たちと関わることで、自然と社会性や協力する力が身についていきます。
非認知能力(集中力・自己表現力)が試される社会への変化
最近はテストの点などの知識だけでなく、「あきらめずに取り組む集中力」「自分の気持ちや考えを上手に伝える力」「友だちと協力して進める力」といった力が、社会でとても重要になっています。
これらは、むずかしい言葉で「非認知能力」と言われることもあります。



非認知能力って具体的にどうやって鍛えるんでしょうか?
勉強だけでは身につかない気がして…。



その通りです。
こうした力は、ただ机で勉強しているだけでは伸びません。
成功したり失敗したりしながら、実際に体験することでどんどん成長していきます。
だからこそ、習い事はピッタリなんです。
例えば、アートの習い事では、正解がない中で自分で考えたり工夫したりする力が育ちます。
さらに、武道や音楽では、集中してがんばる力や、緊張しても力を発揮する心の強さが身につきます。



中学生から始めても遅くありません。
この時期に「がんばる力」や「自分を表す力」をじっくり育てておくことは、将来の仕事選びにもつながる大切な土台になりますよ!
中学生から始めても遅くない! 習い事選びで親が知るべき3つの誤解
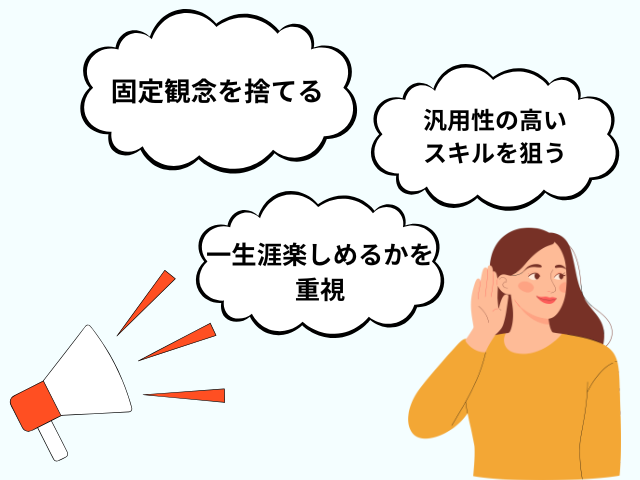
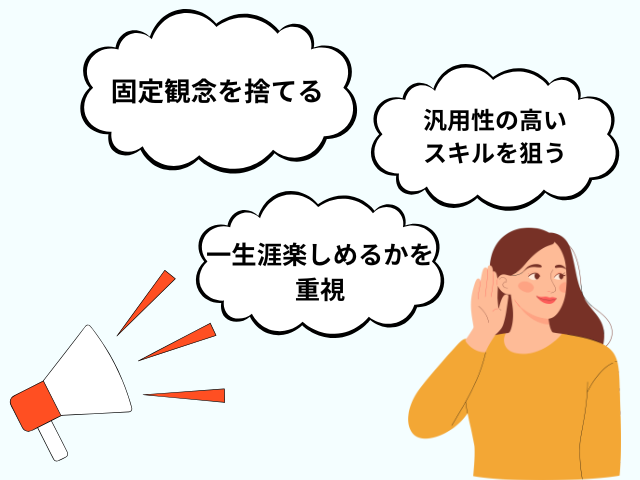
「もう中学生だから新しい習い事はムリ」「部活と両立なんてできない」と思って、やりたいことをはじめるチャンスを逃してしまう人もいます。
でも、中学生から習い事を始めるのには、特別な良さがあります。



この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 部活と習い事は両立できないという固定観念を捨てる
- 専門性を追求するより汎用性の高いスキルを狙うべき理由
- 成果を急ぐより一生涯楽しめるかを重視する判断基準
この時期のお子さんは、自分がどんなことに興味があるか、どんなことが得意かがだんだんはっきりしてくる時期です。
だから、親が決めるのではなく、お子さんが自分で選ぶことがうまくいくポイントです。
部活と習い事は両立できないという固定観念を捨てる


中学生は部活が忙しくなるので、「習い事までしたら大変なんじゃ…」と思う親御さんも多いでしょう。
でも、やり方を工夫すれば両立できます。



両立ってすごく大変そうですが、どうすればうまく回せるでしょうか?



すべてを完璧にやろうとしないことです。
週1回やオンライン形式など、柔軟なスケジュールで取り組める習い事を選び、部活を優先する日を決めておくのがコツです。
こうした工夫をすると、ムリなく続けられます。
そして、部活と習い事を両方することで「限られた時間の中でどう動くか」を自然と考えるようになり、時間の使い方が上手になります。
ただし、「疲れがたまっている」「寝る時間が減っている」「学校生活に影響が出ている」といったサインがあれば、すぐに予定を見直しましょう。



無理をしてまで習い事をする必要はありません。
いちばん大事なのは、楽しむことです!
専門性を追求するより汎用性の高いスキルを狙うべき理由
小さい頃から始める習い事は、一つのことを深く極めることも多いですよね。
でも、中学生から始めるなら、どんな道に進んでも役に立つ「色んな場面で使える力」を身につけるのがおすすめです。



例えばどんな習い事がそれに当たるんでしょうか?



例えば、英会話やプログラミング、作文力などですね。
これらは高校受験や大学での学び、将来のキャリアで必ず役立つ思考のツールになります。
中学生の時期は、まだ将来の進路が定まっていないことがほとんどです。
こういった習い事は、勉強にも受験にも、将来の仕事にも役立ちます。
まだ将来が決まっていないこの時期に、特定の専門だけを深く掘り下げるよりも、どこでも使える基本の力を育てる方が賢い選択になります。
成果を急ぐより一生涯楽しめるかを重視する判断基準
中学生になると、新しい習い事を始めたときに「早く上達してほしい」と思いがちです。
でも、この時期に大切なのは、「その習い事を長く楽しめるかどうか」というポイントです。



目に見える成果がないと、不安になってしまいます。
どう見極めればいいでしょうか?



成果は結果に過ぎません。
まずは、お子さん自身が楽しんでいるか、そして週に一度でもリフレッシュできているかという点に注目しましょう。
中学生は心も体も大きく変わる時期なので、楽しんで続けられる習い事はストレスを減らしてくれたり、自信を持たせてくれたりします。
たとえ上達がゆっくりでも、「好き」という気持ちが続くことがいちばん大事です。



親御さんは、結果よりもがんばる過程をほめてあげると、子どものやる気につながります。
中学生から始めても遅くないスポーツ系の習い事5選


中学生から運動の習い事を始めるのは、体力づくりだけでなく、気持ちの成長にもとてもいいことです。
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 水泳:体への負荷が少なく、運動不足を効果的に解消する
- ダンス:リズム感と自己表現力を高め、学園生活を豊かにする
- 武道(柔道・剣道):礼儀作法と内申点に役立つ精神力を養う
- テニス:個人スキルと生涯スポーツとして楽しめる継続性
- バスケットボール・バレーボール:チームプレイを通じた協調性と連帯感の養成
スポーツを選ぶときは、「どれくらい強くなれるか」よりも「続けやすいか」「何のためにやりたいのか」
を考えることが大切です。



「運動不足を解消したい!」でもいいでしょうか?



もちろんです。
その他にも「友だちと協力する力をつけたい」「ストレス発散したい」など、目的がはっきりしていれば、初心者でも安心して始められます。
それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。
水泳:体への負荷が少なく、運動不足を効果的に解消する
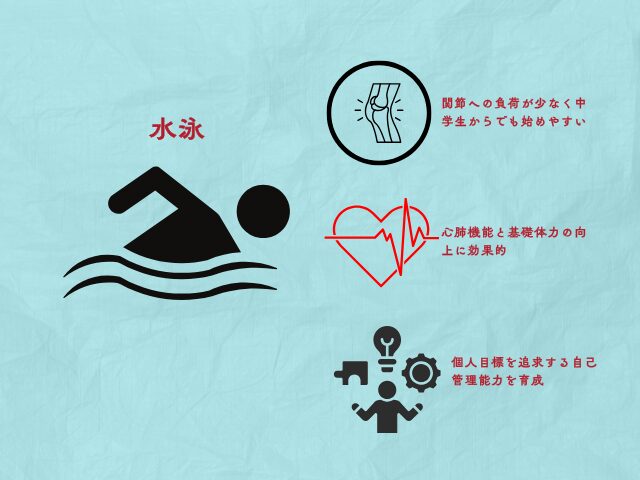
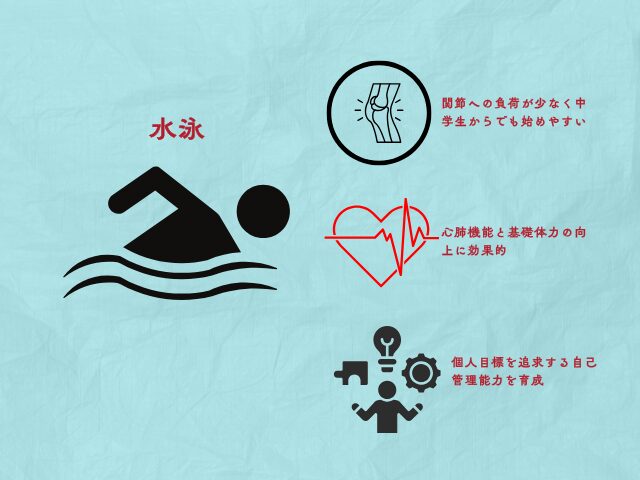
水泳は全身をまんべんなく使うので、体力づくりにとても良いスポーツです。
水の中では体が軽くなるので、ケガもしにくく、中学生からでも始めやすいのがポイントになります。



水泳って、もう今から本格的にやるのは難しい気がしますが、健康のためだけでも価値はありますか?



もちろんです。
泳ぐだけで心臓や肺が強くなり、疲れにくい体になります。
また、水中でリフレッシュできることも大きなメリットです。
中学生になってから泳ぐのが好きになって、週1回だけ通い始めました。最初は25m泳ぐのもやっとだったけど、半年で50mが楽に泳げるように!水の中にいると気持ちが落ち着くので、学校のストレスも減りました。



スイミングスクールには、中学生や初心者向けのクラスも多いので安心です。
ダンス:リズム感と自己表現力を高め、学園生活を豊かにする
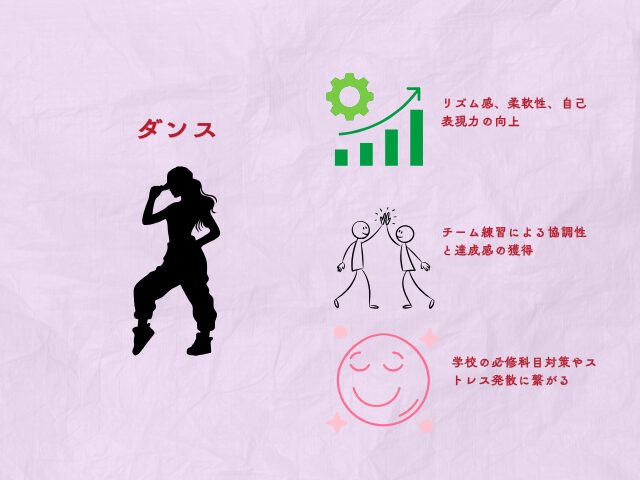
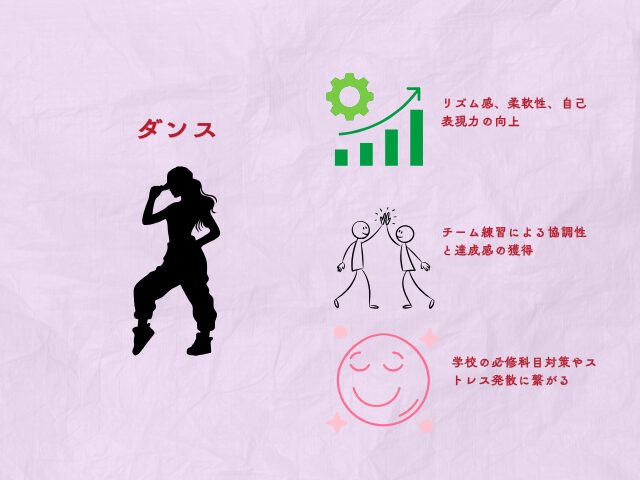
ダンスは、音に合わせて体を動かすのでリズム感が良くなり、柔軟性もアップします。
K-POPやヒップホップなど、好きなジャンルを選べるのも魅力です。



ダンスは運動が苦手な子でも大丈夫でしょうか?
体力的についていけるか心配です。



全く問題ありません。
ダンスは楽しむ気持ちがいちばん大切です。
中学生は体も柔らかい時期なので、すぐにステップが覚えられる子も多いです。
ダンスの授業が学校の必修科目になっている現在、基本的なリズム感やステップを習得しておくことは、学校生活にも役立ちます。
また、発表会やチームでの練習を通じて、仲間と協力し一つの作品を創り上げる協調性や達成感も得られます。
ダンスが苦手だと思っていたけど、体験レッスンに行ったらすごく楽しくて続けています。発表会でみんなと踊ったとき、達成感があって『また頑張ろう!』って思えました。
また、好きなアーティストの振付を真似して踊ったりすることは、日々のストレス発散にも繋がるので、精神的な健康維持にも役立ちます。



学校の授業でダンスがあるので、習っておくと授業にも自信がつくはずです!
ダンスの習い事についての記事を書いています。
この記事では、メリットはもちろん、向いている子の特徴までわかりやすく解説しています。
始めるべきか迷っている親御さんに役立つ内容になっているので、お時間がある方はぜひ読んでみてください。
武道(柔道・剣道):礼儀作法と内申点に役立つ精神力を養う
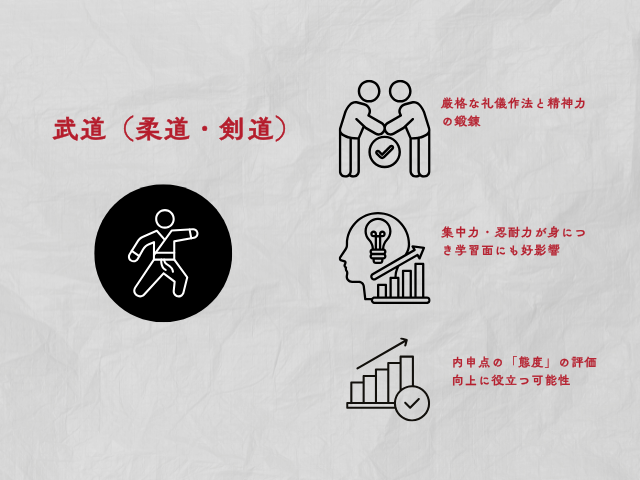
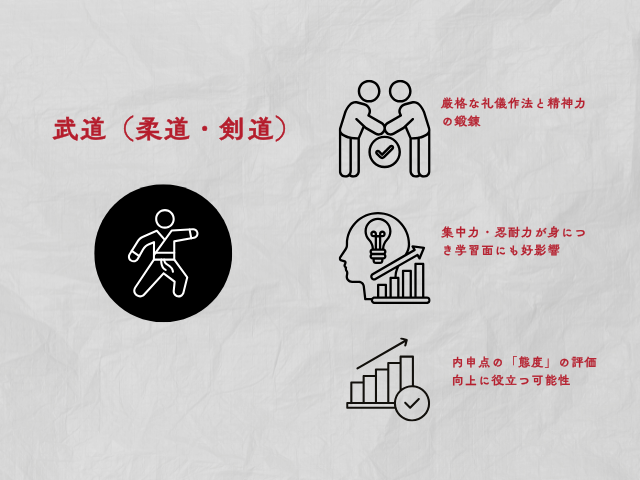
武道は、ただ体を鍛えるだけでなく、挨拶や礼儀がとても大切にされる習い事です。
そのため、中学生からでも遅くありません。精神面の成長にもぴったりです。



武道を習って身についた礼儀作法にはどのようなものがありますか?



うちの子どもは空手を習っているのですが、目上の人への礼儀はもちろん、道場全体に場や相手への敬意を払う姿勢が浸透しています。学校の先生からも、大きな声での返事が素晴らしいと評価されましたよ。
道場では、「礼儀正しい態度」「話を聞く姿勢」「相手を大切にする気持ち」が身につき、学校の生活態度にも良い影響があります。
うちの子は剣道を始めてから、大きな声であいさつできるようになりました。道場では目上の人への礼儀も教えてくれるので、学校の先生にもほめられるようになりました。



集中する力やあきらめない心も鍛えられるので、自信が生まれていきます。
テニス:個人スキルと生涯スポーツとして楽しめる継続性
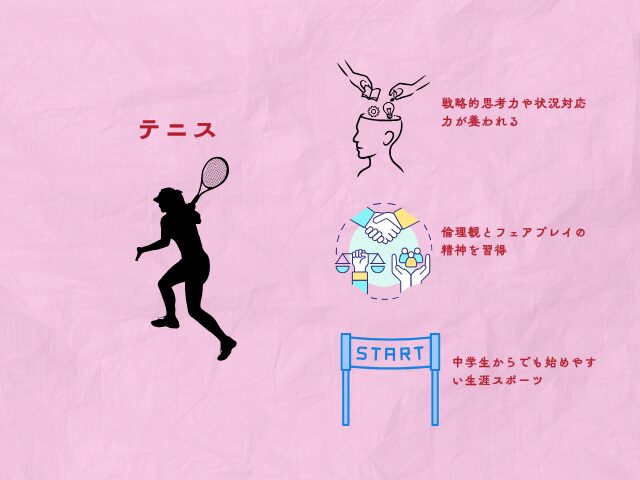
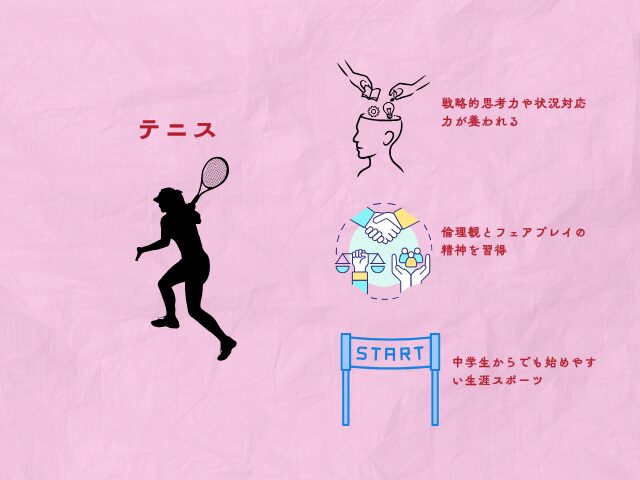
テニスは、中学生からでも始めやすく、初心者クラスがしっかり用意されているスクールが多いです。
相手の動きを見て判断したり、コートのどこに打つか考えたりするので、頭を使うスポーツでもあります。



テニスは経験者が多いイメージですが、中学生から始めるとついていけないでしょうか?



テニススクールなら、中学生の初心者クラスが充実していることが多いです。
個人スキルを重視する競技なので、周りの経験に惑わされず、着実に上達できる環境が整っていますよ。
試合では自分で判定をする場面もあり、フェアな心や責任感も育ちます。
テニスはみんな経験者ばかりだと思っていたけど、スクールには初心者の同級生もいて安心しました。ラリーが少しずつ続くようになると楽しくて、今では週1が楽しみになっています。
また、大人になっても続けやすいスポーツなので、長く楽しめるのも魅力です。
バスケットボール・バレーボール:チームプレイを通じた協調性と連帯感の養成
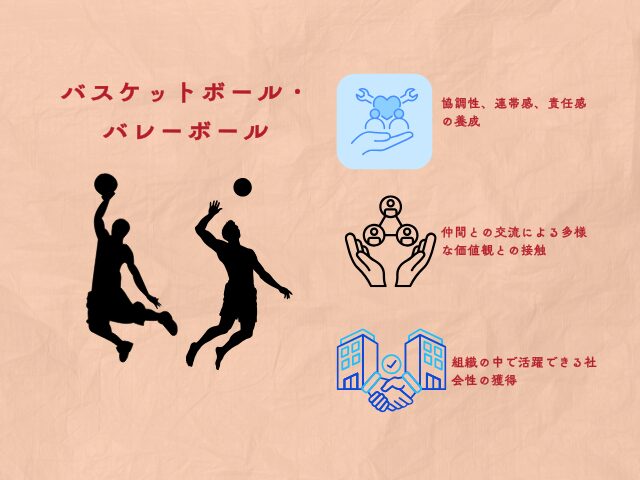
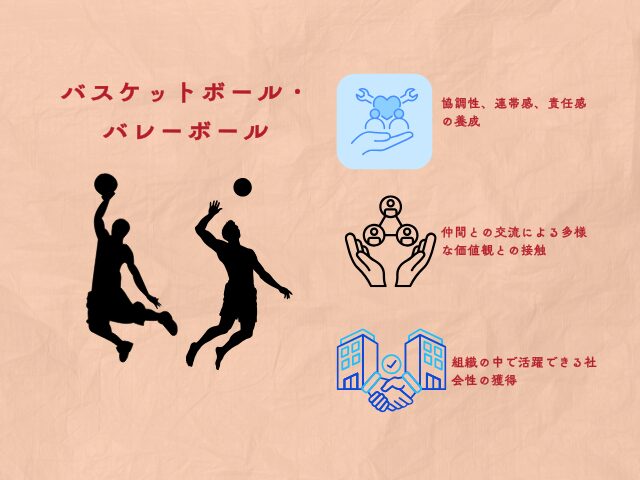
バスケットボールやバレーボールのようなチームスポーツは、みんなで力を合わせることの大切さを学びたい子にぴったりの習い事です。
これらのスポーツでは、まわりの仲間と声をかけ合ったり、パスをつないだりしながら、その場でどう動くかをすぐに考える力が必要になります。
サッカーや野球は、小学生のうちから始める子が多いですが、バスケやバレーは、中学生になってから始める子もたくさんいるスポーツなので安心です。



うちの子は団体行動が少し苦手なのですが、チームスポーツを習うことで変わるでしょうか?



はい、変わるチャンスがあります。
チームスポーツでは、ひとりひとりに「自分の役目」があり、みんなで協力しないとうまくプレーできません。
そのため、「自分のがんばりがチームの力になる」ということを、実際のプレーの中で自然と感じられます。
部活でレギュラーになれなかったり、クラスのメンバーとうまくいかなかった子でも、地域のクラブチームやスクールなら、新しい仲間と気持ちを切り替えてスタートできます。
いろいろな学校の友だちと出会えるので、学校にはない考え方や価値観にふれることができ、とても良い刺激になります。
学校の部活で上手くいかなかったけど、地域のバスケクラブに入ったら新しい友だちができました。試合で点が入ったとき、チーム全員が喜んでくれて、仲間っていいな!と思えるようになりました。
試合で点が入ったときの喜び、仲間と励ましあって乗りこえたときの達成感は、「仲間っていいな」「自分もやればできる!」という気持ちを大きく育ててくれます。
こうした経験を通して身についた協力する力は、大人になってから、どんなグループや職場に入っても役立つ大切な力になります。



チームプレイを通じた協調性といえば、サッカーも当てはまりますよね。
サッカーに関しての記事も書いています。
サッカーの習い事の価値やメリット・デメリットを客観的に解説しています。
迷っている方にぜひ読んでほしい内容です。
中学生の受験・就職で差がつく! 将来に直結するスキルアップ習い事5選


中学生は、「将来どんなことをしたいかな?」と少しずつ考え始める大事な時期です。
この時期に始める習い事は、ただ成績を上げるだけでなく、高校受験・大学受験・社会に出てからもずっと役に立つ力を育ててくれます。
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- プログラミング:論理的思考力とデジタル時代の必須スキル
- 英会話:高校受験とグローバルな視野を広げる最強の武器
- AIスキル:最新技術に触れ未来のキャリアに役立てる
- オンライン学習(通信教育):自分のペースで進められる学習習慣の定着
- 速読・作文:全教科に活きる情報処理能力の土台作り
これから紹介する習い事は、どんな仕事にも使える「一生役立つスキル」が身につくものばかりです。
特に、パソコンや英語の力は、社会でとても大切になるので、中学生のうちから少しずつ始めると将来の選択肢が大きく広がります。



非常に価値のある習い事ばかりです。
一つずつ詳しく確認していきましょう。
プログラミング:論理的思考力とデジタル時代の必須スキル


プログラミングは「コードを書くための勉強」だけではありません。
物ごとをよく見て「どこが問題なのか」「どうしたら直せるのか」を順番に考える力を育ててくれます。
今の時代は、どんな仕事をしていてもパソコンやデジタルツールを使うのが当たり前です。
だから、プログラミングで身につく考え方は、将来どんな道に進む人にも役に立ちます。



プログラミングは難しそうで、中学生からついていけるか心配です。理系の子でないと厳しいでしょうか?



文系・理系は関係なく、興味があれば誰でも始められます。
特に中学生は吸収が早く、ゲーム作りやアプリ作りのように「好きなこと」から入ると楽しく続けられます。
プログラミングを学ぶ中で、「うまく動かないときに何度も挑戦する力」「エラーの原因を探す集中力」「自分で試して改善する力」も自然に身につきます。
ゲームばかりしていた息子に『作る側も面白いよ』とすすめて教室に参加しました。
最初はエラーばかりで落ち込んでいましたが、先生と一緒に原因を探して直せたときの達成感がすごく大きかったようです。
今では『もっとこんなゲームを作りたい!』と自分から勉強するようになり、集中力もぐっと伸びました。
さらに、基礎的な情報処理の力は、高校の「情報」や入試の共通テストの対策にもつながります。



今はオンラインで学べる教室も多く、部活や塾と両立しやすいのもメリットです。
英会話:高校受験とグローバルな視野を広げる最強の武器
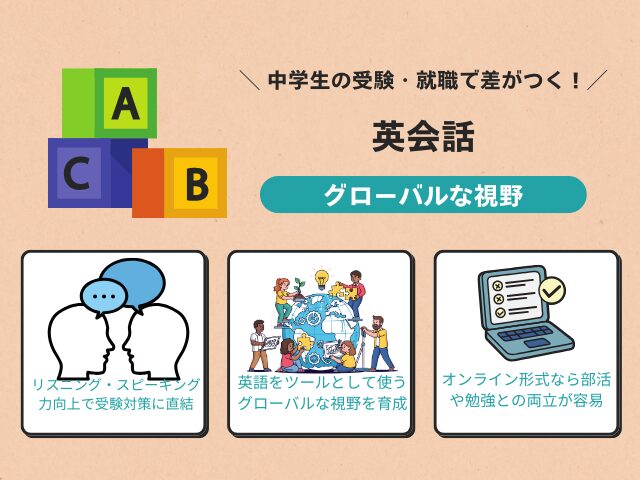
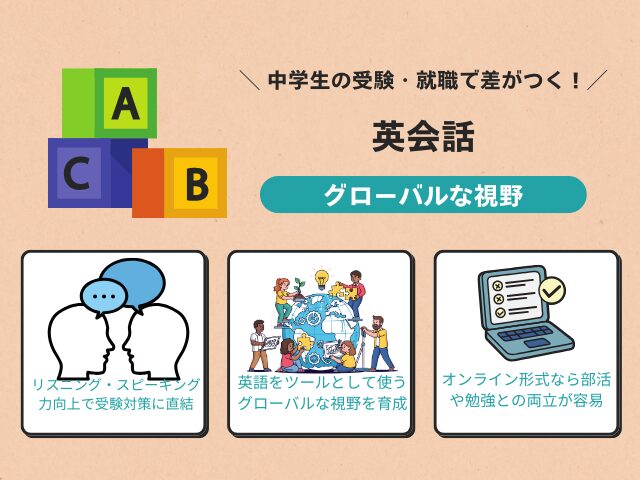
英会話は、高校受験のリスニング・スピーキング対策としてとても役立つ習い事です。
学校や塾のように文法を覚えるだけでなく、「実際に人と話すことで身につく英語」を学べます。
ネイティブの先生と話すことで、「英語って通じるんだ!」という自信が育ち、英語を苦手に感じにくくなります。



単語や文法は塾で習っていますが、英会話は別で必要でしょうか?



ぜひ身につけたいスキルですね!
英会話は、英語を「ツール」として使う訓練になります。
流暢な発音や即座に反応する力は、将来の留学や就職活動で強力な武器となるはずです。
英語力は、グローバルな視野を広げるための最強の武器となります。
オンライン英会話なら、家から受けられるので「部活」「塾」「テスト勉強」と合わせても無理なく続けられます。
英単語を覚えるのは得意でしたが、話すのは苦手で「声が小さい」と学校でも言われていました。
オンライン英会話を始めて数カ月、好きなアニメを先生に説明できたのがすごく嬉しかったようで、そこから英語が楽しくなったみたいです。
発音もはっきりしてきて、リスニングの点数が一気に上がりました。



スピーキングはすぐに伸びるものではないので、中学生のうちに始めておくと大きな差がつきます。
AIスキル:最新技術に触れ未来のキャリアに役立てる


AI(人工知能)は、世の中の仕組みをどんどん変えているとても大きな技術です。
これからの時代、AIを使いこなせるかどうかで、選べる仕事や活躍できる場が大きく変わると言われています。
とはいえ、「AIスキル」と聞くと、とてもむずかしく感じてしまいますよね。
でも、AIを学ぶといっても、いきなり専門家になる必要はありません。



大切なことを簡単にまとめました。
・AIにどうやって指示を出すのか
・AIが何を得意としているのか
・どんな場面で使えるのか



といった 「基礎となる考え方」を身につけることです。



AIスキルなんて、うちの子にはハードルが高すぎる気がします…。
何から始めればいいでしょうか?



そんな心配はしなくて大丈夫です。
まずは、AIに話しかけるように質問や命令をする「プロンプト」の作り方を学んだり、AIがものを判断するために必要な「データ」の仕組みを知ったりするだけで十分です。
難しい専門知識がなくても、「どうやったら伝わりやすい指示ができるか」「思いどおりの答えを引き出すにはどう書けばいいか」を考えることで、論理的に物ごとを組み立てる力が育っていきます。
この 「考える力」は、理系・文系に関係なく、どんな教科の学習にも役立ちます。
AIに興味を持ったきっかけは、自分の好きなゲームの攻略法をAIに質問したことでした。
そこから「もっと上手に質問して、もっと良い答えをもらいたい」という思いが出てきて、AIの学習を始めました。
プロンプトの作り方を覚えるうちに、文章の組み立て方がすごく上手になり、学校の作文の点数も上がったのが驚きでした。
今では「将来はAIを使う仕事がしたい」と自分から話すようになりました。



AIの入門は、プログラミング教室の特別カリキュラムや、オンライン教材でも気軽に学べます。
無理に難しい内容から始めなくても大丈夫です。
オンライン学習(通信教育):自分のペースで進められる学習習慣の定着


オンライン学習や通信教育は、部活や習い事で忙しい中学生にぴったりの学び方です。
スマホやタブレットがあれば、家でも外でも、自分のペースで勉強できます。



オンライン学習のメリットを簡潔にまとめました。
・時間や場所にしばられない
・苦手なところだけ集中して学べる
・自分のペースで復習できる
短い時間でもコツコツ続けることで、自然と学習習慣が身につきます。



塾に通う方が強制力があって良いのでは、と考えてしまうのですが…



もちろん塾にも良い点はたくさんあります。
でも、オンライン学習には「自分で学ぶ力」が育つという大きなメリットがあります。
オンラインなら、「今日はどこを勉強しよう?」「何分やったら終わりにしよう?」と、自分で計画を立てて行動する習慣が身につきます。
これは高校受験を乗り切るために、とても大切な力です。



さらに最近のオンライン教材は、AIがつまずきやすい問題を見つけてくれたり、個別に合った問題を出してくれたりと、とても進化しているんです。
通塾に時間を使わずにすむため、睡眠や休息、他の習い事の時間も確保しやすくなります。
部活が忙しくて塾に通う時間が取れず、オンライン学習に切り替えました。
自分で時間割を作るようにしたところ、勉強のリズムが整って、テスト前に焦ることが少なくなりました。
特にAIの“理解度チェック”はとても便利で、苦手な数学の範囲だけ集中的に練習できたのが良かったようです。
通塾時間がなくなった分、睡眠時間も増え、体調を崩しにくくなりました。
特に、内申点アップを目指す場合、日々の授業を理解しておくことが大切なので、オンライン学習は非常に心強い味方になります。
速読・作文:全教科に活きる情報処理能力の土台作り


速読と作文は、特定の教科だけでなく、すべての学習の基本となる力を高めてくれる習い事です。



中学生になると、教科書やワークの文章量がぐっと増えますよね。
そのときに必要なことをまとめました。
・大量の文を素早く読み取る力
・文章の大事な部分をまとめる力
・自分の考えを人に伝える力
速読では、ただ早く読むのではなく、文章の要点をパッとつかむ読む力を鍛えますが、これにより、むしろ集中力が上がり、理解度も高まると言われています。
作文では、「どう書けば伝わるのか」「どんな順番で説明すればわかりやすいのか」を学びますが、これは高校受験の記述問題や、将来のレポート作成にも大きく役立つのではないでしょうか。



速読って本当に効果があるのでしょうか?
理解力が落ちてしまうのではと心配です。



速読は、ただ速く読む技ではありません。
練習を繰り返すことで、「集中する力」「文章の流れをつかむ力」「必要な情報だけをつかむ力」が育ちます。
そのため、テストの長文問題をスムーズに理解でき、時間に追われにくくなります。
長文を読むのが遅く、テストで最後まで解けないことが悩みでした。
速読教室に通い始めて数カ月、読むスピードよりも“読み方のコツ”が身についたようで、
「どこが大事か分かるようになった!」と本人も嬉しそうでした。
作文の授業では、文章の書き方を丁寧に教えてもらい、学校の作文の評価も上がりました。
今では読解問題に自信を持てるようになり、テストでも点数が安定してきました。
作文と合わせて練習することで、「読む力」と「書く力」が同時に伸び、学力全体の底上げにつながります。
部活に入らない中学生の居場所を作る文化系習い事5選


学校の部活は、多くの中学生が友だちと関わる大切な場所です。



でも、「雰囲気が合わない」興味のある部活がない」と感じる子も少なくありません。
そんなときに力になってくれるのが 「文化系の習い事」 です。
文化系の習い事は、スポーツのように競争が激しいわけではなく、自分の好きなことをじっくり続けられる場所 です。
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 音楽系(楽器・歌):集中力と自己肯定感を高める趣味
- アート系(絵画・デザイン):非認知能力と表現力の強化
- 書道:美しい文字の習得と集中力・精神力の強化
- 写真:独自の視点と記録力を育むクリエイティブな活動
- ボランティア活動:社会性を育み多様な価値観に触れる機会
自分の好きな世界に夢中になれると、自然と自信がつき、それが学校生活をがんばる力にもつながります。



ここからは、中学生に人気の文化系習い事を、くわしく紹介していきますね。
早速、おすすめを見ていきましょう。
音楽系(楽器・歌):集中力と自己肯定感を高める趣味
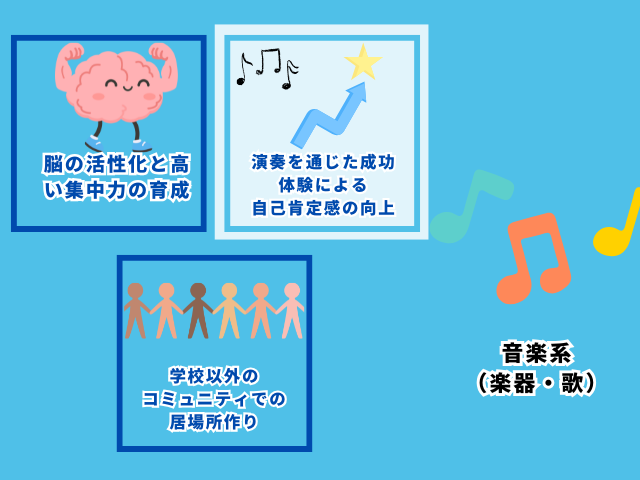
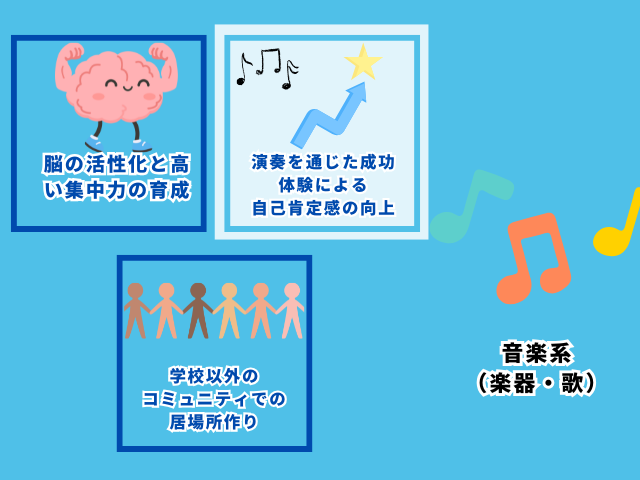
ピアノ、ギター、ドラム、歌などの音楽系の習い事は、楽しみながら集中力を育てられるとても魅力的な活動です。



曲を覚える、楽譜を読む、音を聴き分ける…。
いろいろな動作を同時にするため、自然と頭の回転もよくなります。
中学生から始める子も意外と多く、音楽の授業や合唱コンクールで学んだことが生きるので、ぐんぐん伸びる可能性があります。



練習が面倒になってしまわないか心配です。
どうすれば継続できるでしょうか?



大丈夫です。
音楽は 「自分の好きな曲を選ぶ」だけで、続けやすさが大きく変わります。
好きな曲は何度弾いても飽きませんし、弾けるようになると達成感も大きいです。
さらに、発表会やバンド活動など「人前で披露する場」があると、「また頑張りたい!」という気持ちが自然と湧いてきます。
娘は学校の部活に馴染めず悩んでいましたが、好きだったピアノを習い始めてから、見違えるほど明るくなりました。
好きなアニメ曲を先生と一緒に選んで練習していくのが楽しいようで、毎週「次はこれを弾きたい!」と自分から言っています。
発表会で大きな拍手をもらってからは自信がつき、学校でも前向きに取り組めるようになりました。
音楽教室やオンラインレッスンなら、気の合う仲間に出会えることも多く、学校とはちがう新しい居場所になります。



音楽系の習い事ときくと、ピアノを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
ピアノの習い事についての記事を書いています。
アンケートも実施、体験談もたくさん載せています。
お時間がある方はぜひ読んでみてください!
アート系(絵画・デザイン):非認知能力と表現力の強化


絵画、デッサン、デジタルイラスト、デザインなどのアート系の習い事は、正解が1つではない世界です。
自分が感じたこと、思いついたことをそのまま形にできるので、「自分らしさ」を大事にできる場所になります。



アートを学ぶことで育つ力は、テストの点数には見えにくいですが
将来とても役に立つ重要な力です。
・観察力
・発想力
・自分で考えて工夫する力
・表現力
これらは、社会に出たときに「新しいアイデアを生み出す」ための大切な才能です。



絵を描くのが好きなのですが、受験や就職に役立つでしょうか?
趣味で終わってしまうのではと不安です。



アートを学ぶことで、「Webデザイン」「商品デザイン」「ゲームやアプリのキャラクター制作」など、クリエイティブな分野につながる力が育ちますよ!
家ではよく絵を描いていたのでアート教室に通わせてみたら、「自分の作品をほめてくれる人がいる」という経験が自信につながったようです。
デジタルイラストにも挑戦し、将来はゲームキャラを作りたいと言っています。
家では見られなかった集中力を発揮していて、夢中になれる場所ができて良かったです。
また、絵を描く経験は「人に伝わるプレゼン力」にもつながり、学校でも、社会人になってからも、とても頼れるスキルになります。
書道:美しい文字の習得と集中力・精神力の強化
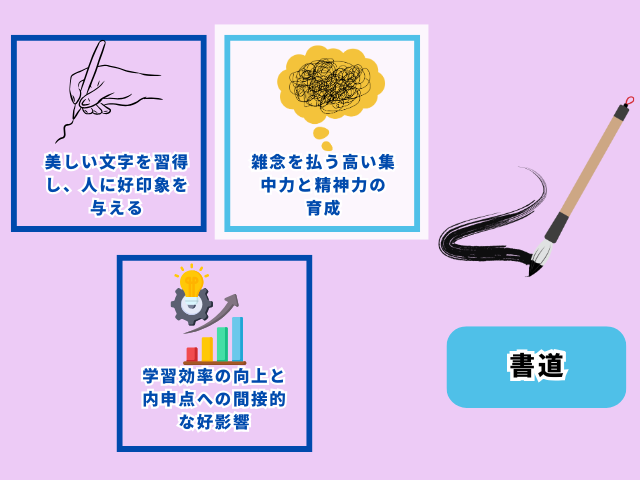
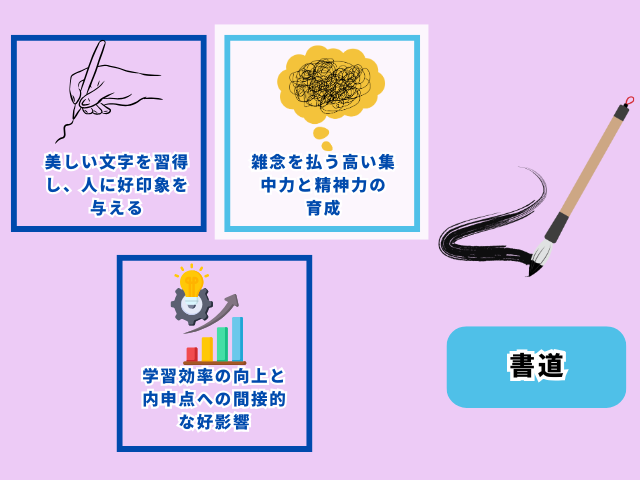
「書道」は昔ながらの習い事に見えますが、実は中学生にとってとても良い効果があります。
筆を持ち、墨の香りを感じながら、一画一画ゆっくり書いていくことで、心が落ち着き、集中力がぐんと伸びます。
スマホやパソコンに慣れた現代の中学生にとって、静かに文字と向き合う時間は、とても貴重です。



書道を続けることのメリットをまとめました。
・ノートが丁寧に書ける
・提出物の印象が良くなる
・テストの文字が読みやすくなる



今は、そもそも文字を書く機会が減っていますよね?
スマホやパソコンで文字を打つことが多く、文字を書く機会も減ってきているのですが、書道を習うことに意味があるのでしょうか?



大いに意味があります。
書道は、ただ文字を書く練習ではありません。
「心のトレーニング」でもあります。
雑念を消して筆を動かすことで、受験勉強に必要な集中力や我慢強さまで育ちます。
テストの時に字が雑になってしまうことが気になり、書道を始めました。
最初は緊張していましたが、筆を動かすうちに気持ちが落ち着くようで、「書いていると頭の中がスッキリする」と本人も言っています。
字がきれいになったことで自信がつき、ノート作りも丁寧になりました。



中学生からでも、「とめ・はね・はらい」を学べば、日常の文字もきれいに変わります。
写真:独自の視点と記録力を育むクリエイティブな活動
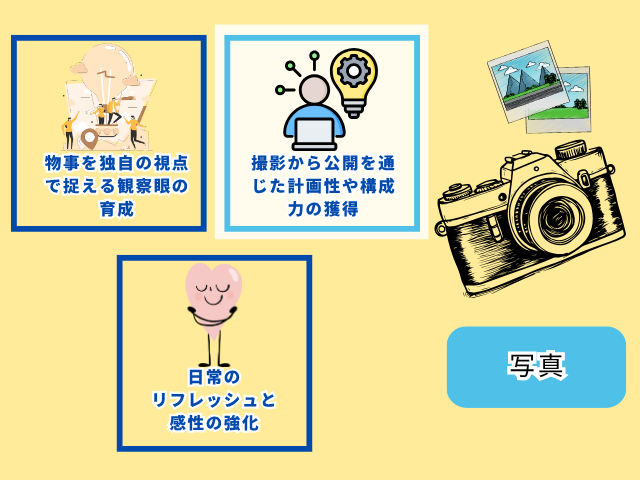
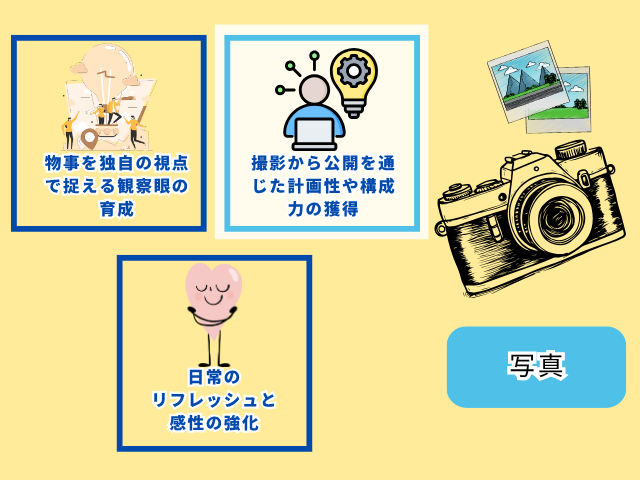
写真は、日常の中にある小さな美しさや面白さを見つける習い事です。
中学生はスマホで気軽に写真を撮れるので、始めやすいのも大きな魅力です。



写真を撮るときには、以外といろいろなことを考えながら撮ります。
それを簡単にまとめました。
・どんな角度で撮る?
・どのタイミングでシャッターを切る?
・主役はどこに置く?



これが観察力や判断力を育ててくれます。
編集作業では、「どんな雰囲気にしたいか」を考えるので、表現力も自然とアップします。
SNSに投稿することで、作品を見てくれる人も増え、学校以外のコミュニティにもつながる可能性があります。



写真に熱中しすぎて、他のことに集中できなくならないか心配です。



ご安心ください。
むしろ良い影響が出ることが多いです。
ゲームばかりだった息子が、写真教室に行くようになって外出が増えました。
風景を撮るのが好きで、歩きながら“どこを撮ろう?”と考えるうちに、自然と観察力がついたように感じます。
SNSに写真を載せてコメントをもらえるのが嬉しいようで、
楽しめる新しい居場所ができました。
写真は「集中する → 休む → 集中する」のリズムが作れるため、心のリフレッシュにも役立ちます。
外に出て景色を撮るだけでも、気分が明るくなります。
ボランティア活動:社会性を育み多様な価値観に触れる機会


ボランティア活動は、「誰かのために行動する」習い事です。
お金のためではなく、地域や人に役立つことを目的として動くので、社会性や思いやりが大きく育つ という特長があります。



主な活動を簡単にまとめてみました!
・地域の清掃
・子ども食堂のお手伝い
・高齢者施設でのサポート



など、中学生でも無理なくできる活動はたくさんありますよ!
普段接しない人たちと関わることで、多様な生き方を知り、視野がぐっと広がります。



ボランティア活動は習い事と呼べるのでしょうか?



はい、立派な体験学習です。
経験を通じて、「コミュニケーション力」「問題解決力」「協調性」
といった社会で必要な力を実践的に学べます。
また、人から感謝される経験は「自分は誰かの役に立てる」という自信を育ててくれます。
娘は学校の人間関係に悩み、家にこもる日が増えていました。
思い切って地域のボランティアに参加させたところ、「ありがとう」と言われる経験が大きな励ましになったようです。
今では月に数回、自分から参加するようになりました。
自分に役割があると感じられたことで、学校生活にも前向きになりました。
高校受験の面接や志望理由書にも活かせるので、中学生にとって非常に価値のある活動です。
失敗しないための「中学生の習い事のやめ時」と親の関わり方


中学生になってから習い事を続けるうえで大切なのは、「いつ、どんな気持ちのときに習い事をやめたらいいのか」を、あらかじめ考えておくことです。
習い事は、ずっと完璧に続けなくても大丈夫です。
お子さんの気持ちや、学校生活の変化によって、見直したり新しいものに挑戦したりするのは自然なことです。



むしろ、状況が変わっているのにムリに続けてしまうと、「時間だけが過ぎてしまった」「お金がもったいなかった」という失敗につながることがあります。
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 3ヶ月で判断!継続する習い事と合わない習い事を見極めるサイン
- 勉強との両立が難しくなった時の優先順位の正しい決め方
- 子どもの意思を尊重しながらサポートする適切な距離感
習い事をやめることは決して悪いことではありません。
大事なのは、「やめる理由」と「次にどう進むか」を前向きに考えることです。
お子さんが安心して次の一歩を踏み出せるよう、親は落ち着いた気持ちでサポートしてあげましょう。



それでは、どんなときが「やめ時」のサインになるのか、そして親がどんなふうに関わればよいのかを、これから詳しく見ていきましょう。
3ヶ月で判断!継続する習い事と合わない習い事を見極めるサイン
習い事がお子さんに合っているかどうかを考えるときの、ひとつの目安が「3ヶ月」です。
新しく始めたばかりのころは、どんな習い事でも不安があったり、うまくできなくて戸惑ったりするものです。
しかし、3ヶ月たっても同じような困りごとが続く場合、その習い事がお子さんに合っていない可能性があります。



3ヶ月ですね。
具体的に、どのようなサインが出たら辞め時だと考えれば良いでしょうか?



まず見ておきたいのは、「習い事に行きたがらない日が増えていないか」という点です。
また、家でまったく練習しなかったり、宿題のような課題に全く手をつけなかったりする場合も、意欲がなくなっているサインです。
お子さん自身が「やりたい」気持ちをすっかり失っているようであれば、その習い事との相性が悪いのかもしれません。
一方で、「続けた方がいい」と分かるサインもあります。
たとえ成長がゆっくりでも、習い事のあとにお子さんの表情が明るくなっていたり、「今日はこんなことができたよ!」と話してくれたりするなら、それはとても良い傾向です。
また、学校の勉強と習い事の内容を結びつけて話すことが増えている場合も、「学んだことが自分の力になっている」という証しです。
このように、習い事をすることで気分がスッキリしたり、できることが増えて自信がついたりしているなら、ゆっくりでも続ける価値があります。



やめる前に、まずは一度相談をしたほうが良いですね。
やめると決める前に、先生やコーチに状況を伝え、「環境を少し変えればうまくいくかどうか」を相談することも大切です。
練習の仕方やクラスのレベルを変えるだけで、急に楽しくなるケースもあります。



お子さんの気持ちだけでなく、周りの大人の意見も参考にしながら、最後はお子さんが前向きに続けられるかどうかで判断しましょう。
勉強との両立が難しくなった時の優先順位の正しい決め方
勉強と習い事を同時に続けるのは、中学生になると特にむずかしくなります。
とくに高校受験が近づくと、「勉強のために習い事をやめた方がいいのかな?」と迷うことが多いです。
でも、習い事をすぐに「やめた方がいいもの」と考える必要はありません。
まずは、習い事の「優先順位」を正しく決めることが大切です。



受験生になったら、やはり全ての習い事を辞めるのが一般的なのでしょうか?



いいえ、必ずしもそうではありません。
英会話や作文など、勉強に役立つ習い事は、続けた方が力になります。
また、運動のように気分転換になる習い事は、逆に勉強の集中力を上げてくれることもあります。
習い事が「何のためにやっているのか」を考えると、優先順位がつけやすくなります。
優先度【低】:なんとなく続けているだけのもの。目的があいまいなもの。
優先度【中】:よい気分転換になるけれど、回数を減らしたり時間を調整できるもの。
優先度【高】:受験や将来に必要な力がつくもの。続けることで心が安定するもの。



全部やめると、逆にうまくいかないこともあります。
習い事をすべてやめてしまうと、ストレスがたまって集中できなくなることがあります。
だから、「やめる」よりも「どうやったら続けられるか」を一度考えてみるのがおすすめです。



前向きに調整することが大事ですね。
お子さんと一緒に優先順位を決めたら、「受験が終わるまでお休みする」「回数を週1回に減らす」など、一時的に調整する方法もあります。



習い事を否定するのではなく、「今は受験をがんばるために形を変えて続ける」という前向きな考え方が大切です。
子どもの意思を尊重しながらサポートする適切な距離感
中学生になると、習い事を続けるために、親のサポートはとても大切です。
でも、一番大事なのは お子さんとの「ちょうどいい距離」 を守ることです。
小さい頃とはちがって、中学生は「自分で決めたい」という気持ちが強くなります。
この気持ちを大切にしてあげることで、習い事を続けやすくなり、成長にもつながります。



つい口出ししてしまったり、進捗を尋ねてしまったりするのですが、どこまで干渉しても良いのでしょうか?



「つい口出しをしてしまう」「進み具合が気になる」
そんな気持ちは、どの親にもあります。
でも、やりすぎは逆効果です。
親がやるべきことは、送迎や費用などのサポートです。
反対に、技術的なことや細かいやり方には口を出さないのが理想だといわれています。
もしお子さんが悩みを話してきたときだけ、静かに話を聞いてあげれば十分です。



親が口出ししすぎるとどうなりますか?
「もっとがんばりなさい」「今日はどれくらいできた?」こうした言葉が多くなると、お子さんはプレッシャーを感じます。
すると、習い事そのものがイヤになり、やる気がなくなることもあります。



お子さんが自分で選んだ習い事なら、練習の時間をどうするか、宿題をどう進めるかも、なるべく自分で決めさせることが大切です。
自分で考えて行動する習慣がつき、将来の力にもなります。
結果を急いで求めるより、「今日もがんばったね」「楽しかった?」と、気持ちに寄りそった声かけをすることで、お子さんは安心します。
その安心感が、習い事を続ける力になります。



習い事でうまくいかない時期があっても、「この子は伸びる力がある」と信じて見守る姿勢 が何よりも大切です。
親がそばで静かに支えてあげることこそ、中学生の習い事を成功へ導く一番のポイントです。
まとめ
いかがでしたか?
中学生からの習い事は、これからの将来に大きな力をくれます。
- 部活の時間が減ってきている今、習い事で新しい経験をふやすことが大事
- プログラミングや英会話など、将来に役立つスキルを今から身につけられる
- 習い事は、学校とはちがう新しい居場所になり、自信も育つ
- 中学生からでも遅くない。自分で考えて行動する力が伸びる
- 親は、口出ししすぎず、子どもの「やってみたい」を応援することが大切
親が前に立つのではなく、お子さんの「やりたい!」という気持ちを大切にしながら、一緒に歩いていくことが何より大事です。
習い事を通して、お子さんの未来の可能性を広げる土台を、今のうちにしっかり作っていきましょう。



家庭によって事情はさまざまなので、この記事を参考にしながら、無理のないぴったりの習い事を選んであげてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。